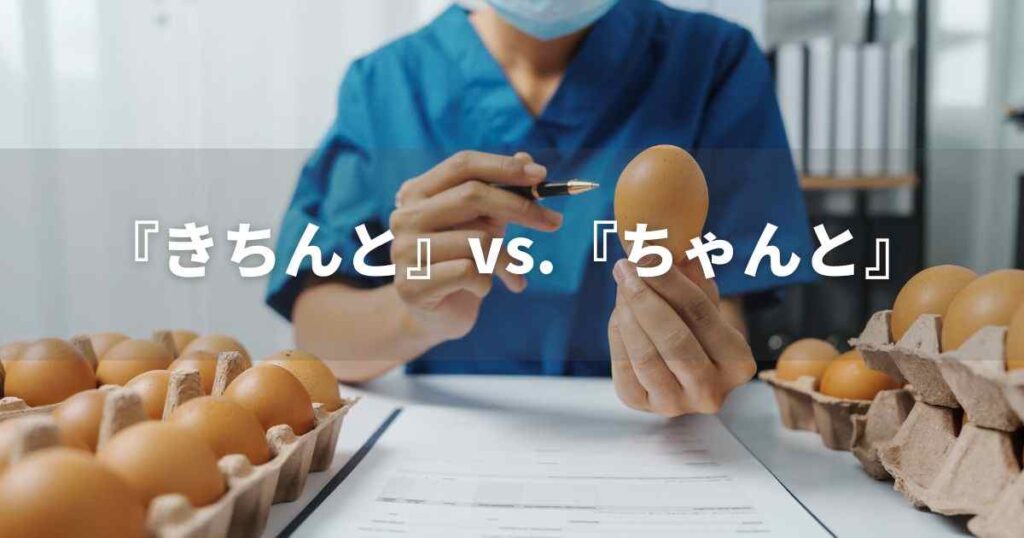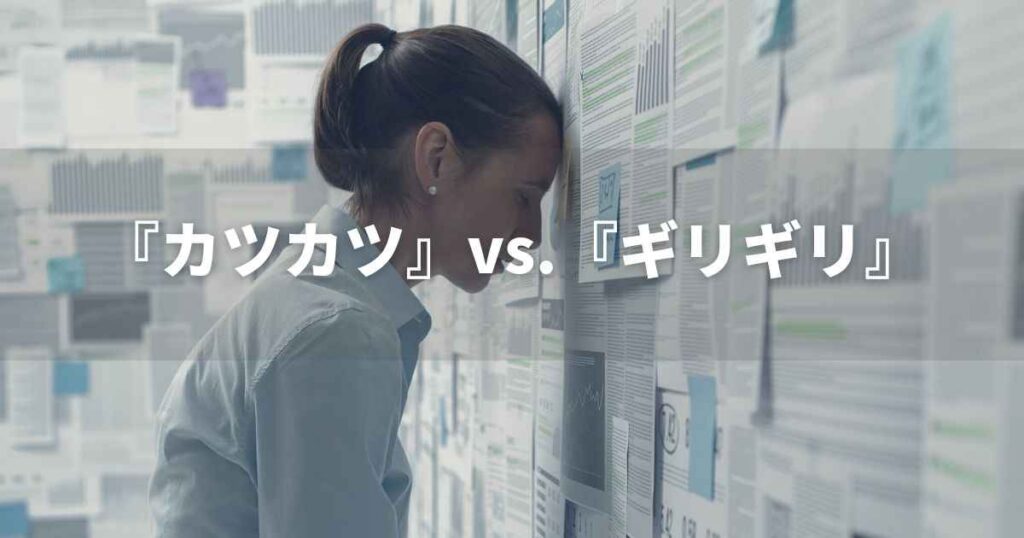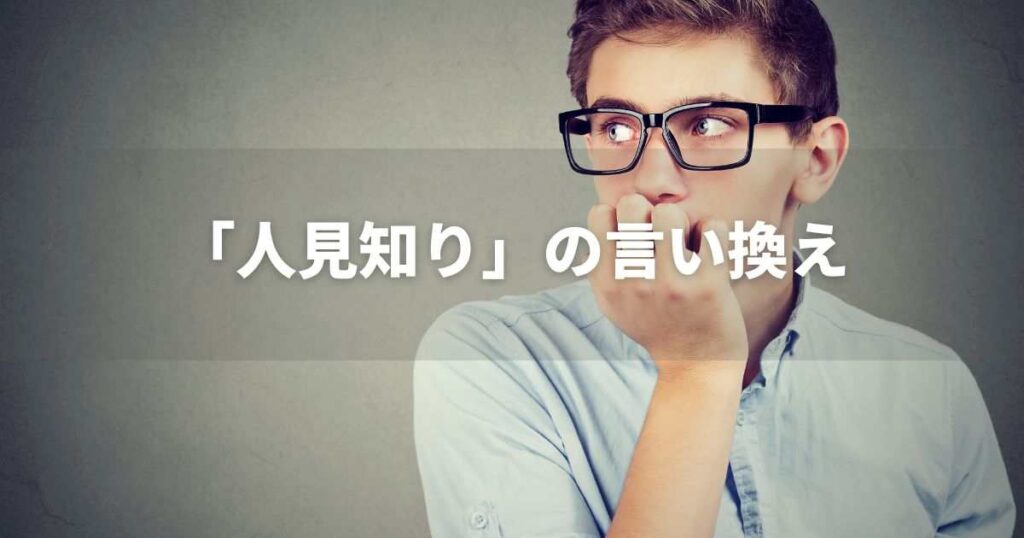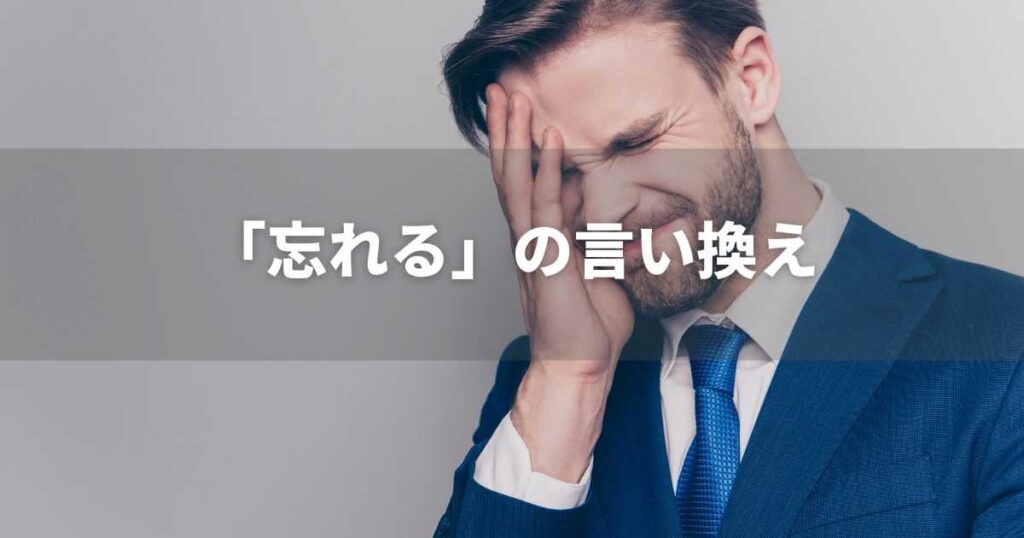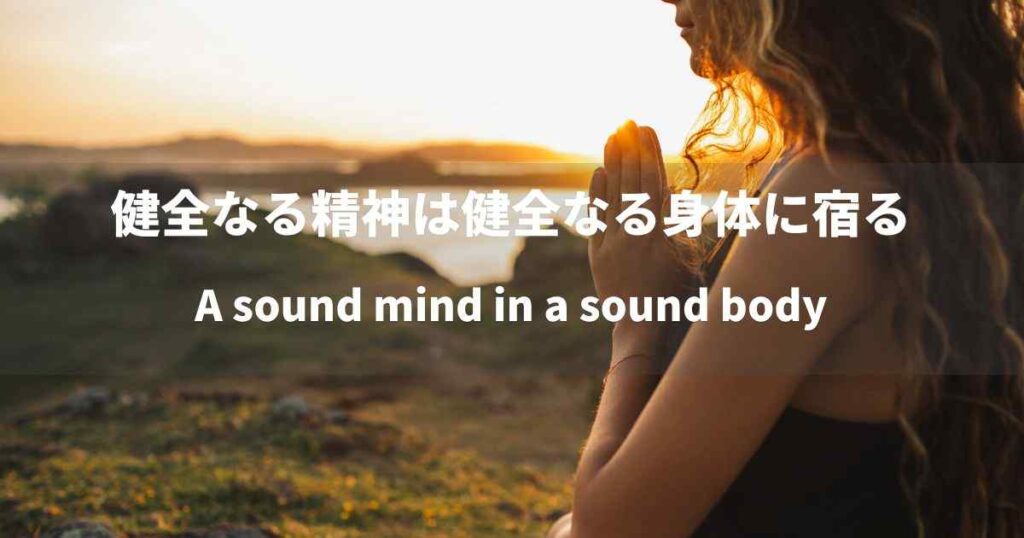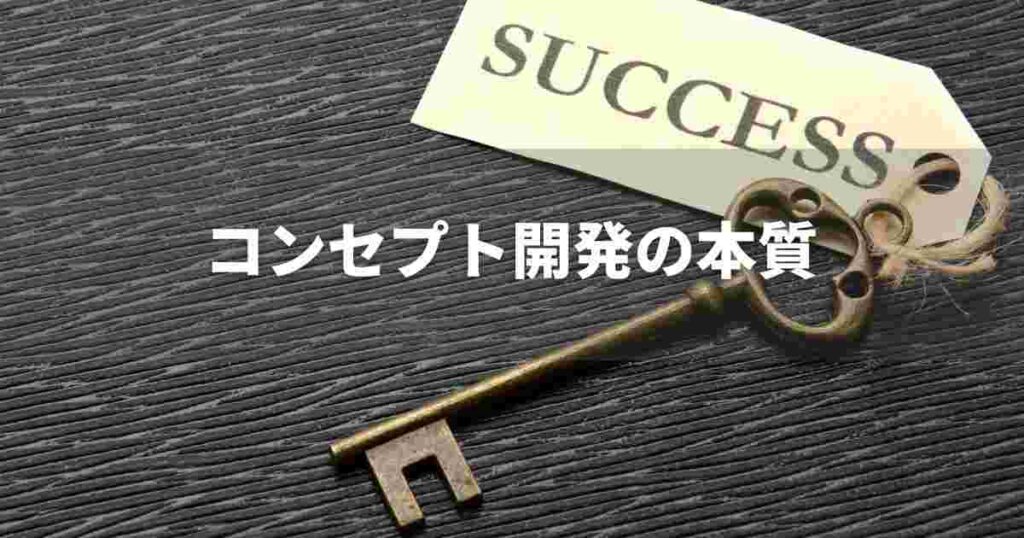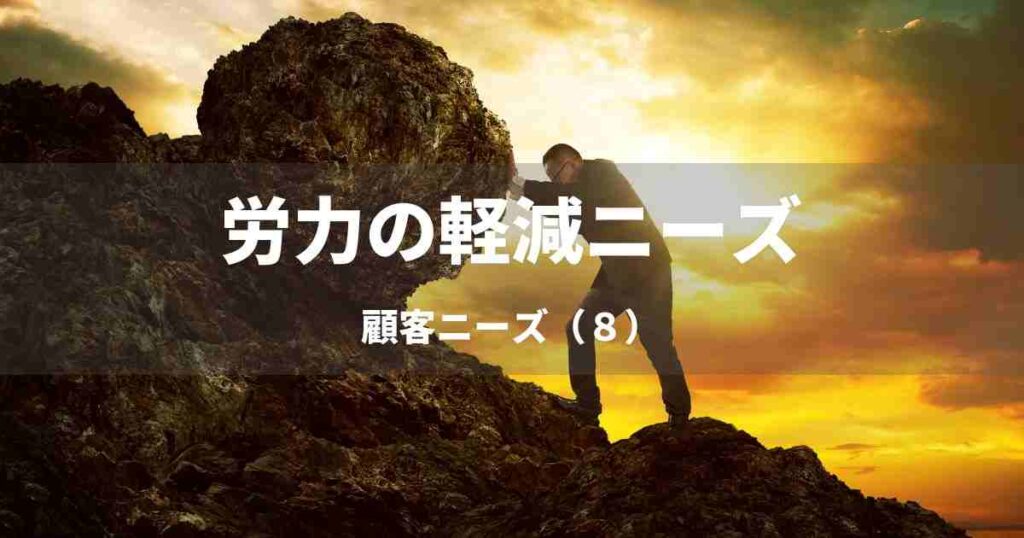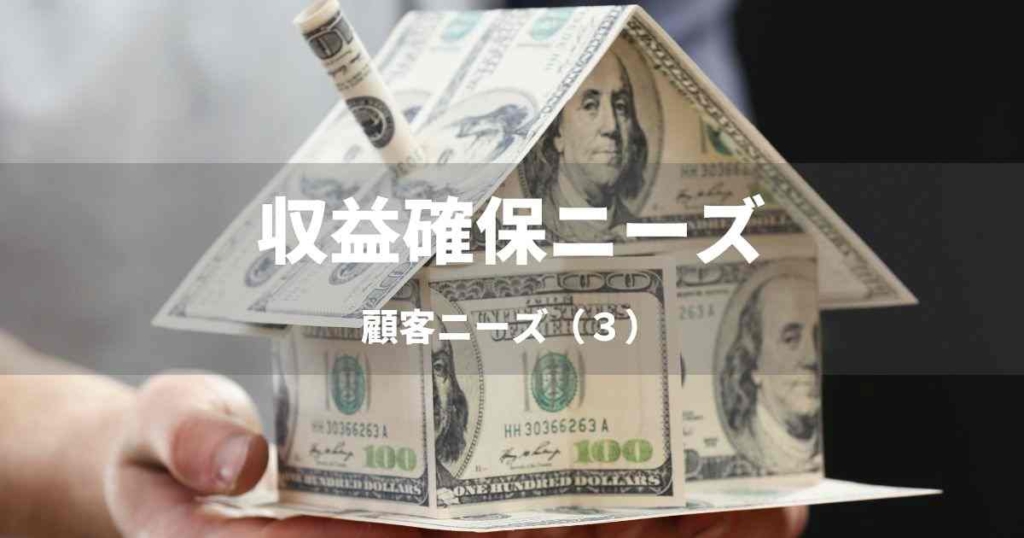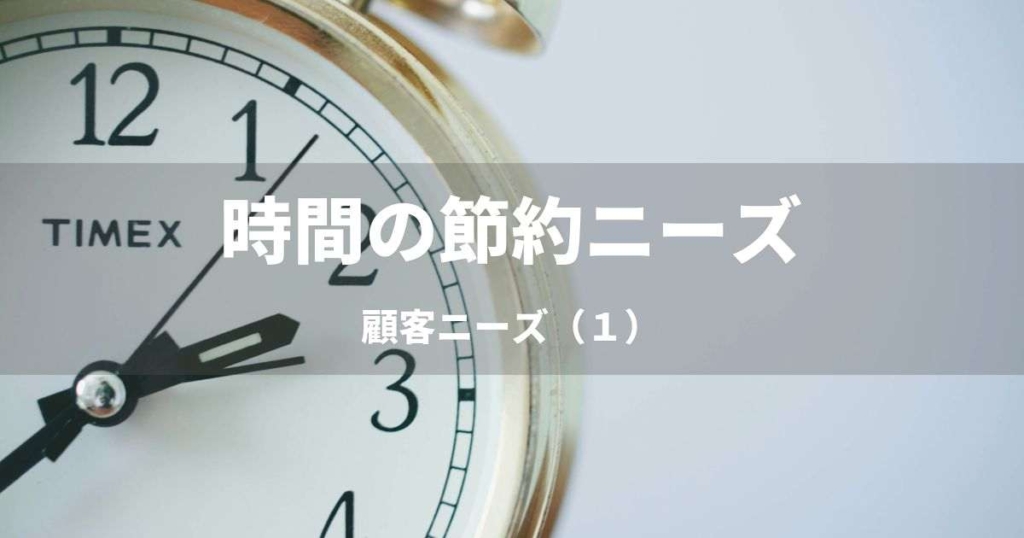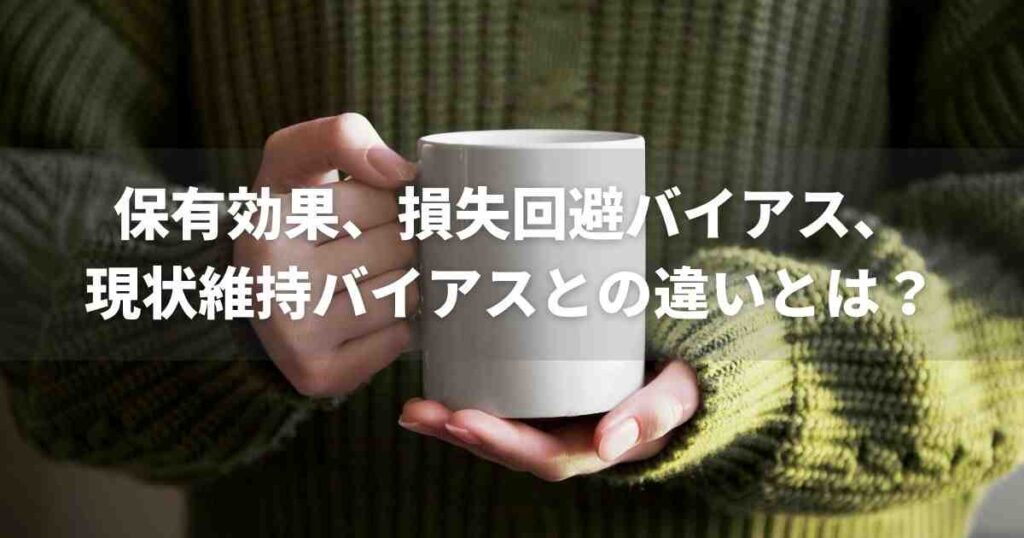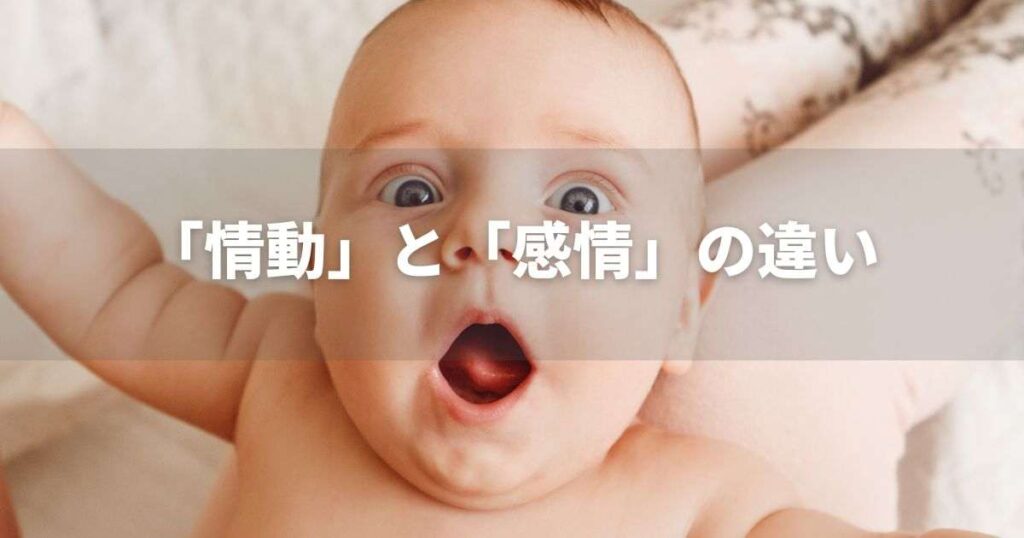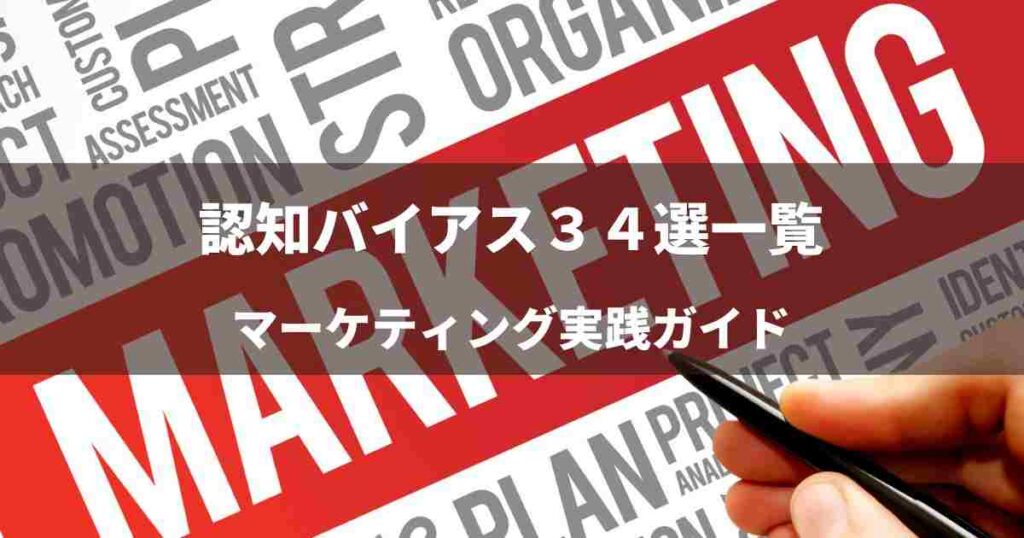-

『きちんと』 『ちゃんと』の違いとは? |類義語使い分け
きちんと vs. ちゃんと ——同じ「整っている」でも、焦点の当て方がまったく違う。 「きちんと」は形式や手順の正確さを示す語、「ちゃんと」は義務や約束を果たす確実さを示す語。 つまり、「形を整えること」に注目するのか、「行為をやり遂げること」... -

『行動』 『行為』の違いとは? |類義語使い分け
行動 vs. 行為 ——同じ「動く」でも、焦点の当て方がまったく違う。 「行動」は意志や目的を伴うプロセス、「行為」は結果としての出来事。つまり、内面の選択に注目するのか、外に現れた結果を評価するのか——そこに2語の分岐点がある。 1.「使い分け」... -

『カツカツ』 『ギリギリ』の違いとは? |類義語使い分け
カツカツ vs. ギリギリ ——「余裕のなさ」にも温度差がある。 カツカツ=余裕を失いながら耐える状態 ギリギリ=限界を越えずに達成する瞬間 1.ことばの「使い分け」が問われる瞬間 「今月の予算、ギリギリだね」「いや、もうカツカツだよ」。 どちらも“... -

『聞く』を品よく言い換えると? ビジネス実践|プロの語彙力
「聞く」は、情報収集、質問、そして依頼の承諾に至るまで、ビジネスコミュニケーションの核となる極めて多機能な動詞である。 その利便性の高さゆえに多用されがちだが、安易な使用は、相手への敬意や真意を読み取ろうとする能動的な姿勢を曖昧にし、言葉... -

『人見知り』をポジティブに言い換えると? 就活・ビジネス実践|プロの語彙力
「人見知り」と聞くとマイナスに捉えられがちだが、実はビジネスに活かせる強みが隠れている。 本記事では、ありがちな自己PRの言い回しから、信頼感ある言い換え表現までを一気通貫で整理。 辞書や類語検索では見つからない「納得できる言い換え」が、こ... -

『優柔不断』をポジティブに言い換えると? 就活・ビジネス実践|プロの語彙力
「優柔不断」をどう言い換えれば、ビジネスの場で前向きに伝わるのか——本記事では、よくある口ぐせの実例から、納得感のある言い換え表現までを体系的に整理。 類語辞典や一般的な記事では拾いきれない「なぜその言い換えが成立するのか」まで踏み込んで解... -

『良い』を品よく言い換えると? ビジネスやレポートに!|プロの語彙力
「良い」は、品質の評価から承認の意思まで、ビジネスのあらゆる場面で飛び交う便利な言葉である。 しかし、この多義的な言葉に安易に頼りすぎると、評価のレベルや意図の重さが読み手に伝わらず、結果的にあなたの発言のプロフェッショナリズムと説得力を... -

『忘れる』を品よく言い換えると? ビジネス実践|プロの語彙力
「忘れる」という表現は、謝罪、依頼、熱中など、あまりにも幅広い文脈で使われるため、便利な一方で、その都度、意図や感情の解像度が著しく低くなる。 特にビジネスシーンでは、単なる「忘れた」という言葉が、謝罪の深さや依頼の丁寧さを曖昧にし、品格... -

『健全なる精神は健全なる身体に宿る』 誤解の歴史とアニメが示す新解釈
「健全なる精神は健全なる身体に宿る」——この言葉は、多くの人が学生時代に一度は耳にしたことがあるだろう。しかし、その真の意味と歴史的経緯を正確に理解している人は少ない。 実はこの格言、約2000年前の古代ローマにまで遡る由来を持ち、現代で広く信... -

『適当』を品よく言い換えると? ビジネス実践|プロの語彙力
「適当」は「最適」から「無責任」まで極めて広い意味をカバーするため、ビジネスの場で安易に使うと、伝えたい意図が曖昧になり、プロとしての信頼性までが揺らぎかねない。 曖昧さに頼るのではなく、言葉の力で情報の解像度を高めることが、知的で品格あ...