絶大な人気を誇るアウトドアブランド
ザ・ノース・フェイス。言わずと知れたアウトドアの人気ブランドだ。
他にも日本で知られるアウトドアブランドといえば、モンベルやパタゴニア、コロンビア、ヘリーハンセン、スノーピークなどいくつもある。
いずれも熱心なファンを抱えている。最近ではワークマンプラスも同ジャンルに仲間入りしたといっていいだろう。
しかし、ノースフェイスの人気は頭一つ抜けているといっていい。
あまりにも人気が続くと、その過剰感から手のひらを返すように消費者離れを招く懸念もあるが、今のところその気配はないようだ。
近年、ブランドの売上げは右肩上がりで、この5年で売上高は倍増し、2020年度には推計で700億円を超えたという(東洋経済オンライン 2022.26)。

おそらくそうした実績の数字より、その人気ぶりは多くの人々が身を持って実感するところだろう。
ノースフェイスのロゴの入ったウェアを着ている人をとにかくよく見かけるのだ。
街行く人もさることながら、バラエティー番組の出演者やニュース番組のフィールドレポーターまで、ふと気づくとノースフェイスを着ている。
また、数々の有名人が愛用していることを公言してはばからない。
ノースフェイスのウエアを着たことのない人でさえ、ついついブランドに親近感を覚えてしまうほどだ。
そんな状況ゆえ、ノースフェイス人気の要因を詳細に考察した報道記事はいくつも見つかる。
しかし、多くの人気ブランドがそうであるように、その成功要因は多分に複合的で、一つや二つの変数に絞り込むのは難しいようだ。
ノースフェイスはどこのブランドか?
ノースフェイスは1966年に米国の西海岸で創業されたブランド。
日本では老舗のスポーツアパレルメーカー、ゴールドウインが長きにわたって輸入販売代理店を務めてきた。
1994年に同社が商標権を取得した以降は、ブランドの哲学は受け継ぎつつ、ゴールドウインが率先して日本独自商品の企画・開発に取り組む。
今では日本で扱うノースフェイス商品の9割は日本オリジナルだという。
ノースフェイスのウエアといえば耐久性や機能性の高さ、着心地のよさなどに定評があるが、そこにはスポーツ分野を専門としてきたメーカーの優れた技術力や開発力が発揮されている。

その一つの例がノースフェイス屈指の人気ダウンジャケット「バルトロ・ライト・ジャケット」だ。
もともとはヒマラヤや南極遠征用の防寒ジャケットで、真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる。
ちなみに商品名の「バルトロ」は南アジアにあるカラコルム山脈の「バルトロ氷河」に由来している。
「バルトロ・ライト・ジャケット」にはゴールドウインの最先端テクノロジーが織り込まれ、極地使用に適した保温性、防風性、耐水性を確保しつつも、着用してみると驚くほど軽い。
街着としては明らかにオーバースペックだが、発売を開始すると、その商品のストーリー性が魅力となって想定以上の売行きとなった。
今ではシーズンごとに「抽選販売方式」になるほどの人気となり、もはや同ジャケットはノースフェイスのアイコン的な存在といっていい。
ノースフェイスが日本市場でこれほど人気を得ている背景には、ダウンジャケットやウインドブレーカー、フリース、リュックなど本格的なアウトドア・アクティビティに耐え得るスペックを備えながら、街着や通勤着などタウンユースとして定着したことがある。
耐久性や機能性に優れ、着心地がいいなら、アウトドアのシーンに限る必要はない。
普段に着たっていいではないか?
そんなノースフェイスからの提案が広く受け入れられたのだ。
ノースフェイスの商品は視界の悪い環境でも視認性が高まるよう鮮やかな原色が使われることが多いが、デザイン自体はいたってシンプルで無駄がない。
そのため着回しがしやすい。
アパレルブランドとは一線を画すデザインも、街着としてはミニマルで洗練された印象につながった。
客層を広げた「コア&モア」戦略
このアウトドアウェアを街着としてまとうスタイルが行き渡る鍵となったのが、ノースフェイスが「コア&モア」と呼ぶ戦略である。
「コア」とは登山を始め、本格的にアウトドアを楽しむ人向けに高度な専門性を追求することをいう。
「モア」とはその「コア」で培った機能性を、幅広いユーザー層に向けた商品に落とし込み、ブランドの汎用性を高める取り組みをいう。
「モア」領域の商品は機能性を街着用に絞り込んでいるため、より買い求めやすい価格に設定されることが多い。
「モア」の領域では近年、レディースやキッズの販売が伸びているという。
その他、ビジネスパーソン向けのリュックやマタニティウエアからもヒット作が生れている。
さらにはグッチやコムデギャルソン、シュプリームなど数々の人気ファッションブランドとのコラボでも話題を呼ぶ。
ターゲットや用途、着用シーンのすそ野を広げる取り組みは着々と進みつつあるのだ。
さらに「モア」の領域は一般ユーザー向けにとどまらない。
スポーツアパレルの専門メーカーらしく、林道や登山道など舗装されていない道を走るトレイルランニングや、五輪種目になったスポーツクライミングなど新たなスポーツ分野にも商品を送り出している。
このように「モア」の領域は常に現在進行形で耳目を集めるが、ノースフェイスは一方で「コア」の領域での象徴的な取り組みにも余念がない。
その一つが同ブランドのフラグシップライン「サミット」シリーズの刷新だ。
ゴールドウインの2017年10月13日付のプレスリリースには「過酷な山岳環境に対応できるウエア」という定義をより明確にし、寒さ、強風、豪雪などハードなコンディション下でも防護性が高く、かつ動きやすいウエアのラインアップを拡充していくとある。積極的なプロモーションにも努めていくという。

THE NORTH FACE「SUMMIT SERIES」をリ… 寒さ、強風、豪雪などでも防護性が高く動きやすいウエアを追求
THE NORTH FACE「SUMMIT SERIES」をリニューアル
かなり限定的なコア層をターゲットにしており、ノースフェイス全体に占める売上げはおそらくわずかであろう。
しかし、ノースフェイスのブランドの気概や矜持(きょうじ)を今一度知らしめるためにも、「サミット」シリーズを引き立てる必要があったのだ。
ちょうどトヨタ自動車でいえば最高級セダン「センチュリー」の位置づけだろう。
トヨタのものづくりへの情熱を込めたブランドで、政府要人に多く利用され、天皇即位の際の祝賀パレードにも使われた。
「サミット」シリーズもまた、実際に南極の観測隊員や日本を代表するアルパインクライマーに愛用されている(ゴールドウイン公式サイト 参照日2022.03.21)。
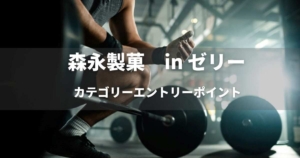
「自主管理店舗」をブランドイメージの発信拠点に

そんな「コア&モア」戦略と連動するのが、ノースフェイスの「自主管理店舗」の展開だ。
スポーツやアウトドアのアパレルブランドを買える店といえば、アルペン、ゼビオといった大手のスポーツ用品店を思い浮かべる人も多いだろう。
事実、ノースフェイスもかつてはそうした販路が中心だった。
それを徐々にノースフェイスが「自主管理店舗」と呼ぶ直営店やショップ・イン・ショップ(店舗内店舗)に軸足を移していったのだ。

チェーン型量販店などいわゆる卸売りによる販路では、売り場の運営はもっぱら販路任せとなる。
商品は店頭で売れて初めて仕入れとみなされる「消化仕入れ」で、売れ残れば返品されるのが一般的だ。
当然ながら、売れ残らないよう在庫を適正管理したり、売れ筋のラインを即座に摑んだりすることは難しい。
そこでノースフェイスは顧客とのリアルな接点をダイレクトに運営できる「自主管理店舗」の比率を徐々に高めていったのだ。
「自主管理店舗」は顧客からのフィードバックが間断なく得られるメリットだけではない。
ノースフェイスのブランドやアウトドア全般に精通する販売スタッフを配しており、同時にブランドの世界観や使命を顧客に伝えられるメリットもある。
いわゆるブランドの発信拠点にもなり得るのだ。
たとえ来店客がスタッフとの対話の機会がなくとも、その品揃えやディスプレイを見るだけでもブランドの奥深さは感じられるだろう。
こうした「自主管理店舗」には統一したフォーマットはなく、立地や客層に応じてストアコンセプトを策定するという(日経クロストレンド 2019.5.9)。
典型的な例が原宿の5つの直営店だ。
その原宿直営店の筆頭、「ザ・ノース・フェイス マウンテン」は同ブランドの旗艦店的な位置づけで、本格的な登山やアウトドアウエアなどブランドのコア・ユーザー向けの商品を扱う。
先に触れたフラグシップライン「サミット」シリーズはここでも展開されている。
同じく原宿の「ザ・ノース・フェイス スタンダード」は街中でアウトドアスタイルを楽しむ都市生活者を、「ザ・ノース・フェイス 3(マーチ)」はアクティブな女性を、「ザ・ノース・フェイス キッズ」は1歳~小学校高学年ぐらいの子どもをそれぞれターゲットにしている。

原宿の5店舗の中でとりわけユニークなのが「ザ・ノース・フェイス オルター」だ。
店舗名の「オルター」は英語の「Alter(変えることの意)」から来ており、自然が元来持つ根源的(プリミティブ)なエネルギーやメカニズムを見直してもらいたいという願いが込められている。
地球環境への負荷低減にも貢献する「プリミティブ&シンプル」なライフスタイルを提案していくという。

「オーバー・ブランディング」のリスクも抑える
こうした「自主管理店舗」がノースフェイスのブランディングに果たした役割は大きい。
実はノースフェイスの「コア&モア」戦略は、ブランディングのセオリーから言えば危うさもはらむ。
多様なシーンで万人が着るようになると、それだけブランドの意味合いが希釈され、やがて陳腐化してしまうリスクもあるのだ。
いわゆる「オーバー・ブランディング(overbranding)」という現象である。
しかし、ノースフェイスは「自主管理店舗」を介してブランドの世界観を継続的に発信し、そのリスクを最小限にとどめてきた。
さながら「最高の体験」を自負するアップルの直営店「アップルストア」のように、店舗の佇(たたず)まいごとブランディングに取り組んだことで、本格派やタウンユーザーを問わず共感を呼び、雪だるま式にファンを増やしていったのだ。
米国生まれのアウトドアブランドに日本屈指のスポーツアパレルメーカーが息を吹き込み、高機能で着心地のよいウエアを次々に世に送り出す。
さらに「コア&モア」戦略によって、コアなファンを大事にしつつ、幅広いユーザー層も開拓していく。
その本来難しいはずの両立をブランドの発信拠点としての「自主管理店舗」が支え、ノースフェイスは絶大な人気を誇るアウトドアブランドへ成長を遂げたのだ。
ノースフェイスのロゴに特異な存在感
そして実はこうしたブランディングの好循環を回す上で強力な「潤滑剤」となったのが、他でもないノースフェイスのロゴである。
そのロゴは他のアウトドアブランドに比べても、形に特徴があって視認されやすい。
待ち合わせの目印になるぐらい遠くからでもよく目立つのだ。
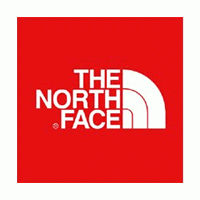
ここでノースフェイスのロゴの由来についても少し触れておこう。
ブランド名のノースフェイスは「北の壁」の意味があり、登山においてもっとも寒さが厳しく一番難関とされるルートのことを指すという。
ハーフドームと言われる鳥かご型のドームを縦に半分に切り落としたような形は、米カリフォルニア州ヨセミテ国立公園にある岩壁がモチーフで、そこはロッククライミングの聖地として知られているらしい。
また、そのハーフドームに入った3本のカーブラインは、「世界三大北壁」であるスイスのアイガー北壁とマッターホルン北壁、フランスのグランジョラス北壁を意味している。
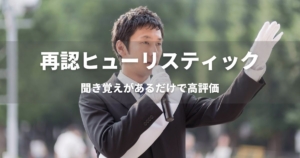
ノースフェイスを取り巻く社会的ネットワーク
この目につきやすいロゴが、人々の間にブランドを広げる上で重要な役割を果たす。
人は社会的ネットワークの中で生きており、自分の考え方や行動様式、あるいは健康状態ですら個人同士のつながりによる影響は免れない。
コロナ禍で人との接触機会が感染を広げるリスクとなる今なら、つながりによって互いに影響を及ぼし合っているとなおのこと実感するだろう。

実は、ブランドの選択もまた、あくまで個人の好みで選んでいると自分では確信していても、いつのまにか周囲の影響を受けていたりするのだ。
とある研究結果によると肥満もまた、社会的ネットワークを辿って伝染するという。
友人が肥満であると高い確率で自分も肥満になりやすい。
しかも、直接の友人ではなく、友人の友人、さらにそのまた友人が肥満であってもなお、自分が肥満になる確率は増す。
友人が高カロリーの食事をとっているのを繰り返し目撃すれば、その行動をついつい自分も真似てしまうらしい。
さらにどこからが「太りすぎ」なのかの線引きも甘くなりやすい。
身近なネットワークの中に肥満の人が存在することで、肥満に対する規範意識や許容度が塗り替えられてしまうのだ。
しかも、その波及効果が知らず知らずのうちに及ぶため、肥満の人を「半面教師」として意識的に抗う機会も逸してしまう。

ノースフェイスがタウンユースとして広がる過程には間違いなく、こうした社会的ネットワークによる伝染があっただろう。
事実、キッズラインの販売が伸びている背景には、若い頃にノースフェイスのファンになった人たちが親世代になり、自分の子どもに着せたくて買っていくことがあるらしい(東洋経済オンライン 2022.02.26)。
これは伝染する経路が極めて鮮明な例だが、その影響は家族や親族内にとどまらない。
強く意識されることはないにせよ、同僚や友人、自分がよく行く街で見かける人たちなどの間でも生じる。
ノースフェイスを着用した人たちの残像が繰り返し脳裏に刻まれ、いつしか感化されていく。
ノースフェイスを一着ぐらい持っていてもいいと思うようになるのだ。
こうした現象は何もノースフェイスに限らない。
人目につきやすい(socially visible)消費財ならよくあることだ。
しかし、ノースフェイスの場合はやはりインパクトのあるロゴがブランドの伝染を加速させる。
人づてに広がったゆえの信頼感が次第にロゴに担保され、さらにそのロゴが人々を惹きつけていく。
評判が評判を呼ぶ格好となるのだ。

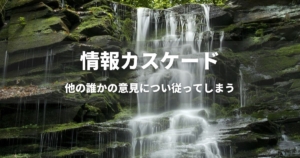
ブランドイメージに「山」の原風景
おそらくノースフェイスはもはやタイムレス(時を超えた)で普遍的なブランドの域に達しており、そう簡単には流行(はや)り廃(すた)りの波に呑まれることはないだろう。
ノースフェイスを初めて買った人が実際に着てみると、軽くて着やすくてしかも丈夫で、百花繚乱のファッションブランドとは一味も二味も違うことを実感する。
おそらく多くの人にとって、ノースフェイスは「ウエアにも機能性がある」ということを最初に気づかせてくれたブランドだろう。
そうした「原体験」を分水嶺に、人々はノースフェイスを別格のブランドと位置付ける。
さらにもう一つ、そこにノースフェイスならではの連想効果が加わってブランドの普遍性を後押しする。
ノースフェイスは、同ブランドにさほど詳しくない人たちにも、「山」の心象風景を想起させるのだ。
おそらくハーフドームのロゴもそんな連想の一助となっているだろう。

「山」は「海」や「星」などと並んで人々の「原風景」の一角を成し、目標や試練、日常を超えたものなどを呼び起こす。
日本でも「山の神」という言い方があるが、「山」は畏敬すべき対象だったりもするのだ。
こうした自然連想による原初的な「山」のイメージは、ノースフェイスのブランドにはプラスに働く。
揺るぎなさや深みが積み増しされ、はやり廃りのない普遍的なブランドのポジションを確固たるものにしていくのだ。
街中でよく見かける馴染み深いノースフェイスは、実はとてもつもなく優秀なブランド・ビルダーでもあったのだ。
米国生まれ、日本育ちの「山の神」の勢いは当分、衰えることはなさそうだ。


- 「過去5年で売り上げ倍増、コロナの逆風跳ね返す ノースフェイス、 『爆発的人気』はいつまで続くか」 2022年02月26日 東洋経済オンライン
- 「主力のメンズに続く『第2、第3の柱』を強化 ノースフェイス、成長のカギ握る『女性と子ども』」2022年02月26日 東洋経済オンライン
- 「寒さ、強風、豪雪などでも防護性が高く動きやすいウエアを追求 THE NORTH FACE『SUMMIT SERIES』をリニューアル」 ゴールドウイン・プレスリリース 2017年10月13日
- 「ザ・ノース・フェイス 強さの秘密 第3回/全5回 ノース・フェイスの直営店が一つずつ異なる理由 店づくりの極意」2019年05月09日 日経クロストレンド
- 「『THE NORTH FACE ALTER』と『THE NORTH FACE MOUNTAIN』が同時オープン」ゴールドウイン・プレスリリース 2019年04月16日
- 「人の健康は『社会とのつながり』が決めていた 喫煙や飲酒、肥満よりも大きな影響がある」2018年6月1日 東洋経済オンライン


