ベビースターラーメンが「料理にちょい足し」という用途開拓に挑み、リブランディングを進めつつある。いわゆる新たなカテゴリーエントリーポイントを確立し、ユーザー層を増やす戦略だ。
人々の生活に脈々と根付いていた「ちょい足し→味変」という文脈にうまく便乗し、「子ども向けのおやつ」から大人にも買ってもらえる「料理の食材」へ間口を広げていく。
その効果は既に見て取れる。
料理に利用したいという意向率が上向き始め、前年割れが続いていた売り上げが回復基調に転じ始めたのだ。
「ちょい足し」とは?
「ちょい足し」という言葉を知っているだろうか?
その意味はなんとなくわかるだろうが、自分の口をついて出たことはないという人もいるかもしれない。
笑える国語辞典には、もともとは「少しだけ足す」の意味で、「定番の料理に食材や調味料などを少し加えることで自分なりの味を創作する」こととある。
「庶民のささやかな創意工夫と食の自由を表現した行為」ともある。
創意工夫とはいかないまでも、ふりかけやそぼろ、削り節などをごはんや料理にかける、混ぜるといったことは誰もが子どものころから繰り返してきた行為の一つだろう。

生活に馴染み過ぎていて、ほぼ意識に上らないレベルに達しているかもしれない。
そして、その何気ない行為に「ちょい足し」というラベルが貼られ、広く用いられるようになったのは深夜番組の人気コーナー「ちょい足しクッキング」がきっかけという。
今ではすっかり市民権を得て、メイクやファッションにまで使われるようになった。
その「ちょい足し」のトレンドにうまく便乗し、伸び悩んでいた売り上げを一気に伸長させたブランドがある。
菓子メーカー「おやつカンパニー」の主力ブランド、「ベビースターラーメン」だ。

顧客基盤先細りの危機感
ベビースターラーメン(以下、ベビースター)は1959年発売のロングセラーブランド。
もともとおやつカンパニーは即席麺の製造販売もしており、製造工程で出てしまう “麺のかけら”を、創業者がアレンジして従業員のおやつとして振舞ったことがきっかけで誕生している(PR TIMES 2022.2.26)。
おそらく40代より上の世代の人なら、近所の駄菓子屋でベビースターを買って食べたという人も多いだろう。

ブランド認知率は97.1%、認知者ベースでの喫食経験率92.3%に達する(Web担当者Forum 2023.4.21)。
しかし、そんなロングセラーブランドのベビースターも2017年ごろまではずっと前年割れが続いていたという。
さらに同ブランドが危機感を強めたのが、将来的な顧客基盤の先細りだ。
ベビースターは「子ども向けのおやつ」という位置づけのお菓子で、ユーザーは通常の菓子カテゴリーの平均のユーザーに比べると30~40代の女性が多い(MarketingBase 2022.9.20)。
子どもの頃に食べていた記憶を持つ親たちが、子どもと一緒に食べたりするのに買うのが主要な購買動機という。
駄菓子屋で自ら買って食べたという懐かしさがそうさせるのだろう。
しかし、この50年で駄菓子屋の数は激減しており、今の若者たちの多くは駄菓子屋で買って食べたという記憶に乏しい。
ブランドが懐かしさの対象にはなり得ないのだ。

その若者たちが結婚して子どもを持っても、ベビースターを子どもと一緒に食べるのに率先して買ってくれるとは考えにくい。
そこで取り組んだのがカテゴリーエントリーポイント(CEP)を増やす作戦だ。
カテゴリーエントリーポイントとは「あっ、こんなときはベビースター」とふと想起してもらう新たなきっかけをつくること。
懐かしさや子どもと一緒に食べるという楽しみ方以外に、新しいベビースターの用途を開拓し、そこで創出した需要をブランドに取り込み、拡売やユーザーの上乗せにつなげようという試みである。

「料理にちょい足し」の用途開拓へ
それが「料理にちょい足しする」という用途だ。
新たに用途を開拓するといっても、0から1を創り出すというのではない。

もともとベビースターは家庭内や飲食店の料理に使われている。もんじゃ焼きの具材としての用途などはその最たる例だろう。
レシピ検索サイトにはベビースターラーメンを使ったレシピが多く投稿されていたという(Web担当者Forum 2023.4.21)。
「料理へのちょい足し」を促進することとは0から1ではなく、1をN倍にする取り組みだったのだ。
料理ブロガーたちと「味変」に挑戦
その「料理にちょい足し」という用途を広げるべく、ベビースターは同ブランド発売60周年を迎えた2018年に新しいキャンペーンをスタートさせる。
情報発信力のある料理ブロガー3名を「ベビースターアンバサダー」として起用し、「ベビースターちょい足しレシピ」を開発して、順次公開していったのだ。

そのキャンペーンのリリース記事(PR TIMES 2018.7.9)には「そのまま食べても美味しいベビースター。こんな美味しいベビースターだから、“ちょい足し”するだけで、苦手な野菜も、ちょっと面倒な料理も、簡単に美味しくしてしまう。」とある。
「簡単に美味しく」、そう、いわゆる「味変」の訴求を狙ったといえる。
「味変」とは文字通り、「食事中に、調味料などで料理の味を変えること」の意味。
即席ラーメンにごまだれをかけて担々麺風にしたり、韓国のコチュジャンをかけて韓国風にしたりといった例がそれである。
山椒(さんしょう)やワサビ、唐辛子などでピリッとした味にアレンジするのも「味変」の定番だろう。
ベビースターはこの「ちょい足し→味変」というトレンドにうまく乗っかろうとしたのだ。
3名の「ベビースターアンバサダー」の就任コメントのなかには「これ、意外とイケるやん!ハマる!」といったレシピを開発していきたいとある。

この意外性、プチサプライズこそ、認知拡大のエンジンとなる。
それをみた人たちがSNSへの投稿意欲を掻き立てられ、さらに自分たちでもひと工夫してベビースターを料理にちょい足ししようとする。
そうした「ネタ消費」の恰好の対象になり得ることをベビースターは見越していたのだろう。
消費者からもレシピを募る
料理ブロガーを起用したキャンペーン以外にも、同じ2018年に日本最大級の料理ブログのポータルサイト「レシピブログ」とコラボし、「ベビースターちょい足しレシピ&フォト」コンテストも実施した。
ベビースターのアイディアレシピやフォトの投稿を募る企画だが、最優秀作品はレシピ動画メディア「DELISH KITCHEN」でレシピの動画が配信される特典がつく。
一方で、ベビースターちょい足しレシピTwitter & Instagram投稿キャンペーンも展開した。
ベビースターの公式アカウントをフォローし、自分のオリジナルレシピをハッシュタグ「#ベビースターちょい足しレシピ」をつけて投稿するという企画だ。
さらに、ベビースターをちょい足しするだけでいつもの料理がグーンとおいしくなるとうたうレシピ本「ベビースターラーメンレシピ – 食卓で大活躍! 簡単&おいしい101品」も出版している。

どんなレシピが生まれたのか?
いずれも、ベビースターによる「ちょい足し→味変」という日常の一コマだった行為を衆目の集める場へと引っ張り出す試みといえる。
では実際にどんなレシピなのだろう?
ここでおやつカンパニーの公式サイトに掲載されているレシピをいくつか挙げてみよう。
「ベビースターでシンガポールチキンライス風」「ベビースターともやしで楽しむかわり皮のまんまるシュウマイ」「食感を楽しむ!ザクザクベビースター麺ととろっと海鮮あんかけ」などがある。
いつものレシピにサッと加えるだけで、料理が味変する。
ベビースターの独特の風味や食感が不思議とマッチし、料理を引き立てていく。
そんな楽しみ方のできるレシピが目白押しなのだ。

「ちょい足し→味変」にピシャリとはまる
この取り組みの効果はてきめんだった。
おやつカンパニーが実施した意識調査では、キャンペーン実施前は3.8%だったベビースターラーメンの料理利用率が、施策後は9.3%へと上昇したという(Web担当者Forum 2023.4.21)。
ベビースターは料理に使う「食材」の仲間入りを果たしたのだ。
そしてその需要を取り込むことにも成功する。
前年割れが続いていた販売実績も回復に向かったという。
この目に見える成果は「ちょい足し→味変」の文脈にベビースターがピシャリとはまったゆえだろう。
当たり役だったとさえいえる。
他のブランドではなかなかこうはいかない。
たとえば、カルピスもかつて新たな用途を開拓しようと、その濃縮液が調味料代わりに使えることの啓発に盛んに取り組んだことがあった。
そのレシピ本によれば、辛いものはまろやかに、こってりしたものはさっぱりと、酸っぱいものはマイルドになるという。
しかし、原形を留(とど)めたまま使うベビースターのほうが「ちょい足し→味変」の文脈には馴染みやすい。
乾麺をそのまま食べる、手軽なお菓子として生まれたベビースターには「ちょい足し」という一瞬の手の動きともしっくりくるのだ。
庶民的で茶目っ気さえあるブランドのパーソナリティも「味変」する発見感や楽しさと相性がいい。

始まった神出鬼没のコラボ企画
その後、ベビースターは2022年に入ると、「おやつの常識を超える」と題したコラボ企画をスタートさせる。

そのキャンペーンのリリース記事(PR TIMES 2022.7.26)には「おやつの常識にとらわれないベビースターならではのオモシロいコラボ企画を、いろいろな業界・いろいろな場所・いろいろなシーンで展開」とある。
「ベビースターがまさかの〇〇に?」と、心弾むコラボ企画が神出鬼没に現れるのだという。
外食チェーンとのコラボ
2022年8月の第一弾のコラボ企画が始まり、1年足らずの間に26回ほどのコラボ企画を重ねている。
たとえば、大阪道頓堀のお好み焼き専門店「千房」や居酒屋チェーンの「つぼ八」などと組んでベビースターを使ったコラボメニューを展開するといった具合だ。
ベビースターが「料理の食材」であることを認めざるを得ない状況をつくり出す、「既成事実化」に一役買ったことは言うまでもない。
トリプルコラボのスニーカー登場
しかし、ベビースターの「常識の超え方」はお菓子から料理の食材になるといったレベルにとどまらなかった。

原宿のスニーカーショップ「atmos(アトモス)」とスニーカーブランド「Reebok」とトリプルコラボし、オリジナルスニーカー「ベビースターラーメンスニーカー」を数量限定の発売もしているのだ。
その神出鬼没ぶりはもはや敬服の念に堪えない。
売り場で想起してもらうために
本ブログでは過去にビスケット菓子「たべっ子どうぶつ」が、そのブランドの特異なキャラクターを生かし、フィギュアや一番くじ、異業種のコラボ商品などと次々にグッズ展開したことを取り上げた。

その一連の取り組みはSNSで話題となり、Z世代を中心とした若者層から思わぬ反響を呼んだのだ。
ベビースターの矢継ぎ早のコラボ企画も意図するところは同じだろう。
スナック菓子は一般に、消費者が各ブランドに強い思い入れを感じることは少ない。
たいていは指名買いではなく、買うたびにブランドスイッチの絶えないバラエティーシーキング型の購買行動となる。
そのため、消費者が売り場に立ったときに、頭の中にブランドを思い浮かべてもらい、購入候補の集合(考慮集合/consideration set)になんとか入れてもらうことが重要となる。

記憶から遠ざかった馴染みの薄いブランドに手が伸びることはまずない。
ベビースターは常に関心を惹きつける事件を起こし、おやつとして、料理の食材として、消費者、とりわけ若い世代の消費者に同ブランドを想起してもらうことを狙ったのだ。

ベビースターの復調ささえた魔法の力
今回の記事ではベビースターが新たなカテゴリーエントリーポイント(CEP)を開拓し、ブランドの復調につなげたことを取り上げた。
懐かしさから子どもと一緒に食べるお菓子といった位置づけだけでは顧客基盤の先細りが危惧されたことが背景にはある。
人々の生活に脈々と根付いていた「ちょい足し→味変」という文脈にねらいを定め、料理にちょい足しするのにベビースターを買ってもらおうと様々なプロモーションを仕掛けたのだ。
実は同ブランドは「ちょい足し→味変」の効果を「ちっちゃな魔法」と呼んでいた。
その魔法はパワーを増し、2022年に入ると、意表を突くコラボ企画が神出鬼没に現れる事態をも引き起こす。
元を正せば「ちょい足し」するという一瞬の手の動き。
その一瞬の手の動きに不思議な力が宿り、ブランドの復調を支えたのだ。

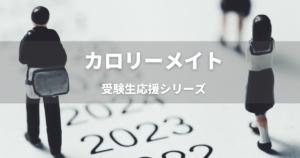

- 「ちょい足し」 笑える国語辞典 (参照日2023年06月20日)
- 「ベビースターラーメンの事例で学ぶ『パーセプション』 世の中の「認識」を変えて売上が増加」 2023年04月21日 Web担当者Forum
- 「認知率97.8%のロングセラー商品『ベビースター』が挑戦し続けるワケ。~VUCA時代に『ベビースター』が届けたい体験とは~」 2022年07月26日 PR TIMES
- 「パーセプション 市場をつくる新発想 ベビースターが抱える老舗のジレンマ レシピ提案で売上11%増」 2021年03月04日 日経クロストレンド
- 「スナック菓子を通じたマーケティングの仮説、実行、検証 ―『CMO Japan Summit 2022』」 2022年09月20日 MarketingBase
- 「『ベビースター』発売60年目記念プロモーション、いよいよ始動! 発売60年目のベビースターの楽しさ、美味しさを再発見できるコンテンツを順次お届け」 2018年07月09日 PR TIMES
- 「8月2日は『ベビースターの日』!ベビースターが〇〇に⁉ゾクゾク出現する、おやつの常識を超える展開について来れるか!?」 2022年07月26日 PR TIMES

