ブランドの本質や精神を3~5語でとらえた言葉、ブランド・マントラ。
ナイキやディズニー、スターバックスなどの世界屈指のブランドはそのマントラを早くから策定し、ブランディングにまつわるすべての活動の羅針盤としている。
ブランドにとっていったい何がふさわしく、何がふさわしくないのか?
細かいルールを定めなくても、ランディングの携わる組織の琴線に触れるマントラさえあれば、自ずと答えは見えてくる。
ブランド・マントラとはどう定義され、どんな局面でブランディングに役立つのか?
本記事では国内外の事例を交えながらその意味するものを紐解いていく。
ブランド・マントラとは?
いつからかブランディングに携わるマーケターのあいだで「ブランド・マントラ」なる言葉がささやかれるようになった。
ブランド・マントラとはブランドの心と魂を3~5語で表現したもの。
もともと「マントラ」とは「特定の音節やフレーズを繰り返し唱えることにより、精神的な力を高めるもの」という意味があるらしい(実用日本語表現辞典)。
「開けゴマ」や「アブラカダブラ」といった呪文のような言葉なのだろう。

そこから転じて個人の信念や目標を表す言葉やフレーズとして使われるようにもなった。
ブランド論の大家、ケビン・ケラー教授はブランド・マントラを以下のように定義している(ザ・ブランド・マーケティング)。
議論の余地のない、ブランド・ポジショニングの本質、または精神をとらえたもの。
ブランドが顧客にとって根本的にどのような存在であるかを社内の従業員および社外のマーケティングパートナーにきちんと理解させ、行動の基準とさせることが目的となる。
基本的には組織やチーム内で意思統一を図る言葉であって、ブランド・スローガンやキャッチコピーのように広告などを介して表に出ていく言葉ではない。
そのケラー教授も著者として名を連ねる「マーケティング・マネジメント 」(16版、コトラー&ケラー&チェルネフ)によれば、ブランド・マントラは時に、その使われ方が正しければ強力な装置になり得ると説く。
もし、仮にその言葉がブランドの競争優位点を端的に言い当てていたとしよう。
するとそのブランドの傘のもと、どんなスペックの商品を投入すべきか、あるいはどのような広告キャンペーンを行うべきか、どんな販売チャネルでどう売っていくのかなどの指針となる。

さらに、その影響力は単なるマーケティング戦術にとどまらない。
たとえば受付カウンターの外観や電話応対など、ブランドにかかわる組織のすみずみにまで影響が及ぶこともあるという。
心のフィルターとして機能する
日本には古来から言葉に霊妙が宿るという「言霊思想」なるものがあるが、ブランド・マントラはそれに近いのもかもしれない。
2023年の「新語・流行語大賞」に18年ぶりのリーグ優勝を果たしたプロ野球・阪神の岡田彰布監督の「アレ(A.R.E.)」が選ばれたが、この言葉に「言霊効果」があったとの指摘もある(日刊スポーツ 2023.9.13)。
「アレ」は本来は「優勝」を意味するが、選手が優勝を意識しすぎず普段通りにプレーできるようにと監督が慮(おもんばか)って考えついた言葉だそうだ。
それがいつしか言霊となり、阪神に優勝をもたらす。
おそらくブランド・マントラもそんな効果をねらった言葉なのだろう。
「マーケティング・マネジメント」にはブランドにふさわしくないマーケティング活動や、顧客の印象に悪影響を及ぼすかもしれないあらゆる行動を排除する「心のフィルター」とある。
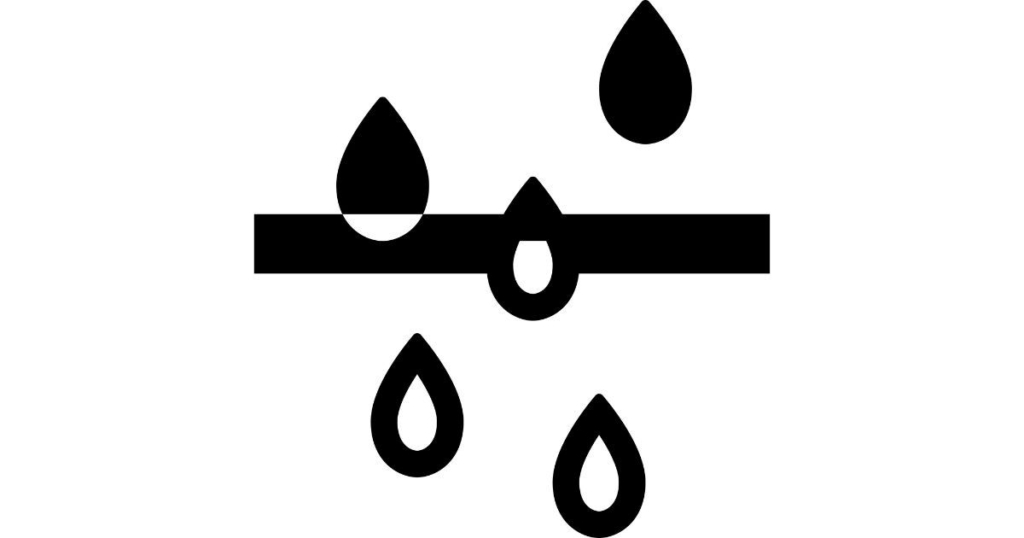
阪神の「アレ」も監督に弁によれば、「コレ」では今にも手が届きそうだし、「アチラ」では遠い感じがしてしまう。「アレ」ぐらいがちょうどいいと思ったという(毎日新聞 2023.12.1) 。
そのカジュアルな、気負いのない響きが過剰なプレッシャーを排除するフィルターとなり、選手たちに平常心を呼び起こしていたのかもしれない。
ナイキのブランド・マントラ
今でこそ、欧米企業でブランド・マントラを策定することはめずらしくなくなったが、最初に言い出したのはナイキだという(ザ・ブランド・マーケティング)。

当時のナイキは進化の途上にあって、ブランド間の競争も厳しく「わかる人にだけわかってもらえればいい」などともはや安穏とはしていられない状況にあった。
そこでナイキは自らのブランドの中核をあらわす価値をできるだけ簡潔に従業員に伝えようとしたのだ。
そんな経緯から生まれたのが「本物のアアスレチック・パフォーマンス(authentic athletic performance)」というブランド・マントラである。
これは何よりまずナイキの真のスポーツへの専心を示す。
開発する商品開発だけではない。
ナイキのいかなる局面のマーケティングプログラムもスポーツの域に照準を当てていなければならない。
どんなに市場ポテンシャルが大きかろうと、ナイキのブランドを冠したままでレジャーやファッションに逸脱してはならないのだ。
さらには「performance」という言葉は、世界最高のアスリートの要求に応えることを常に目指すというナイキの姿勢を示す。
このシンプルなマントラに導かれるように、ナイキは「ランニングシューズ」から「アスレチックシューズ」へ、「アスレチックシューズとアパレル」、「アスレチックに関するすべてのもの」へとそのドメインは拡大してきたのだ(「マーケティング・マネジメント」)。


そして常に、トップアスリートたちのパフォーマンス向上に資する革新性にこだわってきたという。
このナイキの単語3文字のブランド・マントラは組織内において活字になることはなかったらしい。
いわゆる口承伝承(語り継ぐことで口伝えに伝わること)で自然発生的に広がったのだ。
ブランドは本能レベルで感じるものだと信じるナイキらしいエピソードの1つだろう。
ナイキに深く関わる人たちにはどこか琴線に触れる言葉であったため、記憶から遠ざかることもなく、やがて組織内の「集合的記憶」へと上り詰めていったのだ。
ディズニーのブランド・マントラ
さらにナイキと同様、ブランドのドメイン拡張という局面で機能したブランド・マントラがある。
ディズニーの「楽しいファミリー・エンターテイメント(Fun Family Entertainment)」だ。
このマントラが策定されたのが1980年代半ば。
当時のディズニーは広範なライセンスビジネスや業種をまたいだ商品やサービスの投入で驚異的な成長を遂げていたという。


テーマパークやテレビ番組、アニメ映画、キャラクター商品など軒並みヒットしていたのだ。
しかし一方で、ミッキーマウスやドナルドダックなどのキャラクターの不適切使用が表面化していた。
さらにはあまりにも露出が過剰となり、ブランドが陳腐化するという問題も頭をもたげ始めていたのだ。
消費者にはブランド濫用の域に達しているかのように見えていたのである。
その対策の一手が「楽しいファミリー・エンターテイメント」のマントラだったのだ。
ライセンスを供与されたサードパーティ・パートナーが手掛ける商品やサービスも含め、そのマントラにフィルターとしての機能を担わせ、一貫したブランドイメージの構築に努めたのである。
たとえば、ケーブルテレビなどで家庭的価値を伝える番組をディズニーが提供するのは推奨されるが、ディズニー映画をR指定(成人向け)のチャネルで流すのは、どんなにブランドの売り上げに寄与しようとも断じて拒否する。
「楽しいファミリー・エンターテイメント」の精神とは相いれないからだ。
ディズニーの経営陣の弁を借りれば、何も新しいことを創造しようとしたのではなく、ディズニーを特別なブランドにしていた「魔力(マジック)」を呼び戻そうとしたのだという。
なぜ、ブランドが多くの人々に愛されてきたのか、それをひたすら思い起こしてもらう。
ブランド・マントラに担わせる役割はそこにあったのだ。
スターバックスのブランド・マントラ
もう1つ、ブランドのビジネスに大きく貢献したマントラにスターバックスの「日常を潤す至福のひととき(Rewarding Everyday Moments)」がある。
このマントラを策定するにあたって意識したのは「コーヒー」という言葉を避けることだったという。
スターバックスはあくまでサードプレイス(third place/第三の場所)であり、自宅や学校、職場とは趣(おもむき)を異にする居心地のいい居場所である。


そこで楽しめるのが紅茶であっても、フラペチーノであっても、くつろげる空間であってもかまわない。
日常を潤す至福のひとときを顧客に提供することがブランドの使命なのだ。
さらに「everyday(日常)」にもスターバックスの強い思い入れがあった。
スターバックスは顧客が至福の体験を求めて昨日訪れたら、また今日も訪れたくなる、そして明日も訪れたくなる場所にならなければならない。
たった3つの単語のブランド・マントラはスターバックスが何たるブランドか、その本質を全従業員に示す金言となっていたといえよう。
PCメーカーVAIOのブランド・マントラ
ブランド・マントラという言い方はしていないが、日本にも言葉にブランドの本質的価値を託し、従業員たちを鼓舞しようする企業は存在する。
その1つがPCメーカーのVAIO(2014年にソニーから独立)だ。

同社は従業員全員を同じベクトルに向かわせようと、商品理念の以下の3つの言葉に集約している。
- カッコイイ(Inspiring)
- カシコイ(Ingenious)
- ホンモノ(Genuine)
「カッコイイ」は見た目のデザインだけでなく、ブランドの歴史や機能性を含めた、心がワクワクしてくるようなカッコよさをさす。
「カシコイ」は人間の能力を飛躍的に高めるPCの本領が独創性を伴って発揮されていることをさす。
「ホンモノ」は高い質感や品位が感じられ、長く使っても価値が減らないことを意味するのだという。
いずれもVAIOのPCが何であり、何でないのかを判断する際、従業員たちが立ち返る言葉になっている。
ブランド・マントラに代わるもの
ブランド・マントラとはやや位相が異なるが、本ブログでも組織のリーダーが語る特定の言葉が影響力を放っている例はいくつか取り上げている。
ワークマンであれば「声のする方に、進化する。」、アイリスオーヤマであれば「ユーザーイン発想」、ZARAであれば「片手は工場に、もう一つの手は顧客に」などがそれだ。
それらの言葉が従業員たちの心に深く根を張って、判断や行動に影響を与えているのだ。



また、言葉ではないものの、サッポロビールの黒ラベルに使われている金星のロゴマークも、ブランド・マントラに匹敵する効果を放ったはずだ。
黒の背景に大きな金色の星となれば、どこか超然とした雰囲気を醸し出す。

同じマークはサッポロの企業ブランドにも使われており、そのモチーフは北極星で、一番星である北極星を目指した開拓使たちの精神性を表現しているのだという。
同ブランドが社外に向けて打ち出す「丸くなるな、星になれ」というメッセージもその精神性に通じるものがあるだろう。
ブランドがどうあるべきかを指し示し、マーケティングや営業の担当者、飲食店や小売店など、主要なステークホルダーにとって目指すべき北極星、すなわち天空の羅針盤になっていたに違いない。
その成果の1つがブランドへの共感を誘う「大人エレベーター」のCMだろう。
ビールブランドでは珍しく異例の長期スパンで展開している。
そうした黒ラベルの孤高を保つスタンスも、軸足がぶれない人たちが飲むというユーザーイメージにつながっている。

優れたブランド・マントラの要件
今回の記事ではブランド・マントラについてブランド論の識者や実務家らの見解を交えながら解説してきた。
この記事のしめくくりとして、「マーケティング・マネジメント」に書かれていた優れたブランド・マントラの3つの要件を紹介しておこう。
ブランド・マントラが組織やチームにおいて有効に機能するためには以下の3つの基準を満たす必要あるという。
- ブランドのユニークな点を端的に伝えていること。それと同時にブランドがどんなカテゴリーに立脚するのかが明確にイメージできること。
- ブランドの本質をシンプルに表現したものであること。短くて、さわやかで、生き生きとした意味を有していることが望ましい。
- できるだけ多くの従業員にとって個人的に意味があること。ブランドのことを考えただけで気持ちが奮い立つほど、従業員たちが自分とブランドには深い関わりがあると感じられる言葉であること。
たがが言葉、されど言葉。
記事の冒頭で触れた「ブランドの心と魂を3~5語で表現したもの」というブランド・マントラの定義はまさに言い得て妙といえる。
一朝一夕で見つかるものではないが、ブランディングに関わるマーケターならブランド・マントラなる言葉を探す旅に出てみるのも一考に値するだろう。


