消費者の頭のなかにおけるブランドの「ユニークな位置取り」を意味するポジショニング。
マーケティングの世界ではブランドの成否を決めると言っても過言ではない重要コンセプトだ。
その提唱者のアル・ライズ、ジャック・トラウトによれば、実はブランドのネーミングの決断がポジショニング戦略で圧倒的な優位に立つためには極めて重要だという。
提唱者2人が推すのはブランドの便益や使うメリットが瞬時に伝わるブランド名だという。
とはいえ、あまり製品特性に寄り過ぎてもいけない。
絶妙な加減を見極めながらひとひねりするが必要らしい。
本記事では2人が挙げた秀逸な事例を振り返りながら、その深意に迫っていく。
ネーミングとポジショニング戦略
近代マーケティングの父と称されるフィリップ・コトラーが革命的なコンセプトと呼んだ「ポジショニング」。
消費者の頭のなかにおけるブランドの「ユニークな位置取り」を意味する。
その位置取りが叶うことで、消費者はブランドを思い出しやすくなり(純粋想起)、競合との明確な違いを認識し(独自性)、結果的に買ってみよう(購買動機)という気持ちになる。
今から半世紀以上も前、気鋭のマーケターであるアル・ライズ、ジャック・トラウトが提唱したコンセプトだ。
そのコンセプトは1982年に出版された「Positioning: The Battle for Your Mind」にわかりやすく説かれている。
日本語訳の「ポジショニング戦略 新版」が2008年に出版されているが、「世界中で30年間読み継がれる、マーケターのバイブル」というのが触れ込みだ。
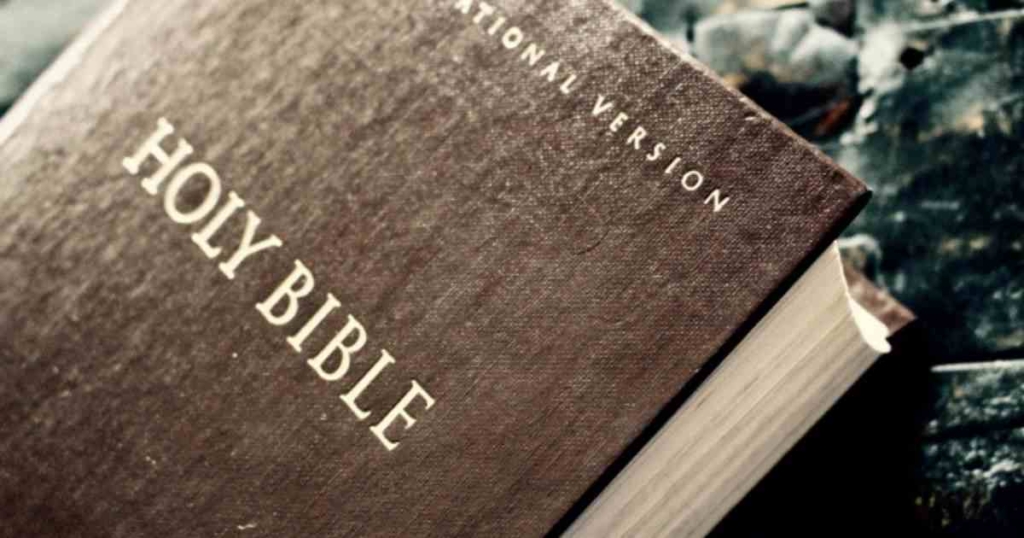
実はそのマーケターのバイブルともいえる著書のなかでアル・ライズ、ジャック・トラウトがとても興味深い主張をしている。
ネーミングとポジショニング戦略との関係だ。
ポジショニング戦略で圧倒的な優位に立つためにはネーミングの決断が極めて重要と断言している。

ブランドの便益が瞬時に伝わるネーミング
2人が秀逸なネーミングとして挙げた例をいくつか紹介しよう。
いずれもそのネーミングがポジショニング戦略上の優位性につながっているという。
- シャンプーの「ヘッド&ショルダーズ」
- スキンケアローションの「インテンシブケア」
- 歯磨き粉の「クローズアップ」(顔を寄せ合っても安心の意)
- 高耐久電池「ダイハード」
- シェービングクリーム「エッジ」(すっきりした剃り味の意)
ブランドの便益や、その最大のメリットが瞬時に伝わること。
ポジショニング戦略で優位に立ちたいなら、ネーミングはそれに尽きると2人は主張する。
何気なくつけられた無意味な名まえでは消費者の頭のなかに斬り込むことはずっと難しいという。
しかし、世のなかを広く見渡せば、そんなルールに反するネーミングで成功しているブランドも多々ある。
たとえば、「シボレー」はフランスのレースドライバーの名まえであり、「メルセデス」においてはパリ駐在外交官令嬢の名まえだ。

ブランドの便益やそのメリットを示唆する名まえとはとてもいえない。
コカ・コーラやコダック、ゼロックスなどは無意味語によるネーミングの最たる例だろう。
しかし、そうした名まえは市場にブランドの選択肢が少なかったころに成功を手にしている。
消費者の頭のなかに真っ先に切り込み、それゆえ「先発優位」が遺憾なく発揮できたのである。
ところが、今やブランドの選択肢は市場に急増し、生き馬の目を抜くような競争が繰り広げられている(アル・ライズ、ジャック・トラウトは脳に集中砲火を浴びている状態と著書に書いている)。
無意味語によるネーミングはもはや通用しないのだ。
過去の無意味語ネーミングの成功例にとらわれて、判断を誤ってはいけないとアル・ライズ、ジャック・トラウトの2人はいう。


一般名詞化のリスクは避ける
その一方で、ブランドの製品特性そのものに寄り添い過ぎた名まえもリスクが伴うと2人は警鐘を鳴らす。
その典型例として挙げられているのが、ミラーのライトビール「ミラー・ライト」だ。

一時は成功を収めたものの、ブランド名にライト(light)との形容詞を用いたことが後に徒(あだ)となった。
競合ブランドの追随を許してしまったのだ。
シュリッツ・ライト、クアーズ・ライト、バド・ライトなどが次々に発売される。
「〇〇・ライト」がいわゆる一般名詞化してしまったのである。
日本でもセロテープやウォシュレット、宅急便といったとき、思い出すのはそれらのブランドの商標権を持つニチバンやTOTO、ヤマト運輸だけではないだろう。

ネーミングはぎりぎりの線を突け!
アル・ライズ、ジャック・トラウトは「ほとんど一般名詞だが、完全に一般名詞ではない」というギリギリの線をねらうのがよいと著書に書いている。

そのぎりぎりの線を突いた例をいくつか挙げてみよう。
ピープル(People) vs. アス(US)
どちらも米国のいわゆるゴシップ雑誌であるが、その体(てい)を言い当てているのは断然「ピープル」だろう。
実際、「ピープル」は好調が続くが、後追いした「アス(US)」は苦戦を強いられているという。
タイム vs. ニューズウィーク
「タイム」も「ニューズウィーク」のどちらも成功を収めているニュース週刊誌だ。
しかし、アル・ライズ、ジャック・トラウトはニュース週刊誌らしさを体現した名まえという点で「ニューズウィーク」に軍配を上げている。
実際、広告収入は「タイム」を上回っているという。
「タイム」は簡潔で覚えやすいものの、やや曖昧さをはらむのだ。
必ずしもニュース週刊誌の名まえでなくともよく、たとえば時計業界誌にも十分使えるだろう。
「ニューズウィーク」に比べるとニュース週刊誌の典型性(プロトタイプ性)という点で見劣りしてしまう。
エスクァイア vs. プレイボーイ
「エスクァイア(Esquire)」は都会の若者向け雑誌として先行していたものの、のちに「プレイボーイ」に首位の座を明け渡すことになる。
「プレイボーイ」のほうが一般的でイメージを湧きやすく、その射程が広い。
より多くの読者を捉えることができるのだ。
ヨッティングvs. セイルマガジン
マリンスポーツ誌をけん引していた「ヨッティング」だが、ヨット人口は減少傾向にある。
そんななか、「ヨッティング」を猛烈な追い上げを受けているのが「セイルマガジン」だ。
この名まえは「プレイボーイ」と同様、間口がより広くとれるというメリットがある。
プリンターズ・インクvs. アドバタイジング・エイジ
これら2つは広告業界誌だ。
広告がほぼ新聞か雑誌に限られていた時代は「プリンターズ・インク」でも十分に成功を収めることができていた。
しかし、広告がテレビやラジオを含め4マス媒体の時代を迎えると「アドバタイジング・エイジ」が躍進することになる。
ここまで挙げてきた「ピープル」「ニューズウィーク」「プレイボーイ」「セイルマガジン」「アドバタイジング・エイジ」。
そうした勝ち組のネーミングは「名は体を表す」式で急所を突き、ポジショニング戦略上優位に立った。
しかも、ライバルブランドに比べ、時代の趨勢ともうまく「レレバンス(関連性・妥当性)」を保ち、結果的に人々の購買動機を刺激することに成功している。
今日性や時代感に乏しい印象の名まえでは、人々の間にブランドに対する心理的関与が生まれにくくなるのだ。


大事なのは「レレバンス」を保つこと
この「レレバンス」については、消費者ニーズや時代感覚との整合性という点で、アル・ライズとジャック・トラウトは興味深い事例を2つ挙げている。
イースタン航空
1つが米国のイースタン航空だ。
「自由主義世界で第2位の旅客航空会社」とのスローガンを掲げ、一時は4大航空会社の1つとも言われている同社だが、業績は芳しくない。
「イースタン」という地域限定的な社名のせいで、全米を幅広く飛んでいるにもかかわらず、ニューヨークやボストンなど東海岸だけを飛んでいるとの印象を与えてしまうのだ。
アメリカンやユナイテッドなどの全国規模の航空会社に比べると、「レレバンス」が弱く、時代に逆行したイメージが拭えない。
思い切って改名するという手もあるだろう。
実際、やはりローカル航空会社と捉えられがちだったアレゲニー航空はUSエアに生まれ変わっている。
マーガリン
もう一つの事例がマーガリンだ。
この得体のしれない名まえのせいで、未だにマーガリンはバターのまがいものだと思われていると2人は指摘する。

そして、「ソイ(大豆)・バター」と命名すべきだったというのだ。
「ピーナッツ・バター」と同様に原材料の示す名まえである。
あえて乳製品のバターと対置する大豆製のバターと打ち出すことで、そのポジショニングが明確になる。
健康志向の高まりで大豆など植物性の原材料に注目が集まれば、「レレバンス」も高まり、業績にも跳ね返ってくるだろう。
マーガリンではその恩恵に浴することはできないのだ。


ポジショニング戦略成功の陰にネーミングあり
「名が体を表す」式のネーミング
今回の記事ではネーミングとポジショニング戦略の関係について、ポジショニングの提唱者、アル・ライズ、ジャック・トラウトの主張をまとめた。
2人は絶妙な加減の見極めが必要としつつも、基本は「名が体を表す」式のネーミングを推している。
そんな名まえをブランドにつけることで、ブランドの明確なポジショニングが可能となり、カテゴリーニーズが発生したときにほかのどのブランドよりも先に想起され、購入の候補として躍り出る。
それが成功法則だと2人はいう。
著書に挙げられていた例も非常にわかりやすく説得力がある。
対照的な白紙のキャンパス理論
しかし、一方でネーミングの世界では対照的な考え方があることにも触れておこう。

ネーミングの「白紙のキャンパス」理論というものだ。
「空き瓶」理論という言い方もするらしい。
ブランド論の大家であるデービッド・A・アーカー氏が著書「ブランド・エクイティ戦略」で紹介しているが、どんな連想も持たない名まえ、無意味語に近い名まえをあえてつけることを指す。
「白紙のキャンパス」理論によるネーミングでは、ブランドの名まえは無意味語ゆえ、純粋に一から商品特性や広告、パッケージなどで意味づけしていくことになる。
白紙のキャンパスに創造力を羽ばたかせ、自由に描いていく感覚だろう。
そうしたネーミングの例として、アーカーはコーヒーブランドの「MJB」やフイルムの「コダック」、ハンバーガーチェーンの「ウェンディーズ」を挙げている。


カテゴリーごとにつきまとう既存の連想から解放され、ブランド独自の世界観を打ち出すことができる点がメリットといえよう。
さらにどんなカテゴリーともくっつくことができるため、カテゴリーを超えたブランド拡張にも柔軟に対応できるようになる。
たかが名まえ、されど名まえ
2020年代の今、アル・ライズ、ジャック・トラウトのネーミングに関する主張はやや極論に思えるかしれない。
2人が見据えた1970年代より、市場環境はさらに爛熟化しており、商品カテゴリーによって「白紙のキャンパス理論」が有効な場合もあるだろう。
「名まえ」を自由に意味づけることができる上、複数のカテゴリーにまたがったブランド拡張が柔軟に行えるのは、それなりのリスクも伴うが大きな魅力だろう。
それでも結局は、名まえに代わる何らかのキーワードを決める必要が出てくる。
ポジショニング戦略が成功裏に進むよう、ブランドに携わるチームが一丸となって意味づけに取り組む必要があるのだ。
たかが名まえ、されど名まえである。
ネーミングとポジショニング戦略との密なる関係をマーケターは頭の片隅に入れておくべきだろう。




