後知恵バイアスとは?
後知恵バイアスとは起こってしまった出来事を最初から分かっていたかのように思い込む傾向をいう。
「やっぱりね。そうなると思っていた」「だからいったじゃないか」など、結果を知った後に、その出来事が起こることを予測していたかのように錯覚してしまう。

自分の責任が問われない状況なら、責めるような口調になることもしばしばだろう。
ただし、自分のミスや失敗に対しても後知恵バイアスはすり寄ってくる。
「あとのとき、ああすればよかった」などと、つい「たられば(もし…していたら、もし…していれば)」をあれこれ考えてしまい、後悔や自責の念などに苦しむことにもなるのだ。
後知恵バイアスはポジティブな結果に対しても生じることはある。
たとえば、ひいきのスポーツチームが接戦を制して辛勝した際、「自分は絶対勝つと思っていた」というときがそうだろう。
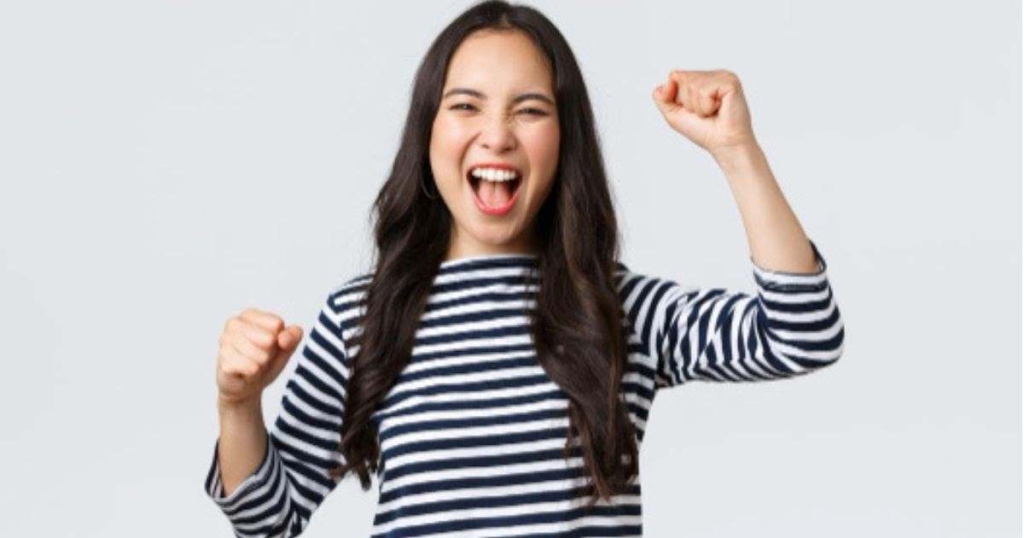

しかし、総じてネガティブな結果のときに後知恵バイアスは生じやすいようだ。
日常のあるある具体例
後知恵バイアスの事例をいくつか挙げてみよう。
他者が何らかの不運や災難に見舞われたとき、心の中で以下のようにつぶやいたことはないだろうか?
- 有名人が不祥事を起こしたとき→「あの人ならやらかすと思っていた」
- 他部門のプロジェクトが失敗に終わったとき→「最初から失敗すると思っていた」
- 遭難事故の事後情報を報道で耳にしたとき→「そんなことになぜ注意を怠ったのか」
- ひいきのチームが試合に負けたとき→「もっと早くから選手を交替させるべきだった」

自分の身に不幸がふりかかったときもしかりだ。
たとえば以下のようなことが頭をよぎるのは日常的だろう。
- テスト後に問題の答えを知ったとき→「ちょっと考えれば解けていたはずだ」
- 道に迷ったとき→「あのとき、引き返すべきだった」
- 恋愛が不幸な終わり方をしたとき→「あのとき、強くひきとめておくべきだった」
- 投資で損失を出したとき→「あのとき、もっと調べておけば損はしなかった」

後知恵バイアスは身近な認知バイアス(認知のゆがみの意)の1つだ。
隙あらばいたることろで起きるといっていい。
調査や実験が示す後知恵バイアス
後知恵バイアスが生じることを定量的に調べた結果が心理学者らによっていくつも報告されている。
ここで2つほど紹介しておこう。
米国大統領選挙の当選予測
1つは米国の大統領選挙の当選予測に関する調査結果だ。
その調査では開票前に「民主党と共和党の候補のうち、どちらの候補が当選すると思うか?」と質問をしている。
その回答と、結果がわかった後に「開票前の時点でどちらの候補が当選すると思っていたか?」と質問した際の回答を比較したのだ(サクッとわかるビジネス教養 認知バイアス)。
すると開票前に比べ、結果がわかった後の回答のほうが実際に当選した候補の名前を挙げる割合がずっと高かったという。
当選結果に影響を受ける形で自分が予測した候補者を答えてしまったのだ。
おそらくそこに嘘をつこうという気持ちはなく、後知恵バイアスが介在することで、無意識のうちに自分の予測にまつわる記憶を修正してしまったのだろう。
プロジェクトの結末予測
もう1つの報告では、心理学の実験法によって後知恵バイアスを裏付けている(意思決定のマネジメント)。
実験参加者にはある企業の新規事業のプロジェクトの概要を読んで失敗するか成功するかを予測してもらう。

その際、参加者を2つのグループに分け、一方のグループは予測する前にそのプロジェクトが「成功」ないし「失敗」するといういずれかの結末を知らされる。
その上で(そのプロジェクトの結末を知らなかったものとして)予測してもらった。
もう一方のグループは事前に何も知らせず単純に予測してもらうのみだった。
両グループの予測を比較すると、事前に結末を知らされたグループは、知らされなかったグループに比べ、知らされた結末に引っ張られる形で予測をしたという。
読んだのは同じ文面だったが、やはりそこにも後知恵バイアスが働き、予測に大きな開きが生まれたといえよう。
たいていは無意識に起こる
大統領候補の当選予測にせよ、プロジェクトの成功予測にせよ、いったん結果がわかってしまうと多くの人が後知恵バイアスから逃れられなくなる。
傍(はた)からみれば、「後出し」「後講釈」しているようにも思える。
たしかに現実の世界ではそうやって相手にマウントを取ろうとする人もいるだろう。
しかし、後知恵バイアスは本人の自覚のないところで起こり、善良な人たちが素直にそう確信していることも少なくない。
後知恵バイアスが生じる理由
不確かな記憶のメカニズム
ではなぜ、後知恵バイアスはいとも簡単に起こるのか?
これは人の普遍的な記憶のメカニズムが関係している。
人が何かを思い出すとき、考えたことや体験したことが録画した映像のようにそのまま再生されるわけではない。
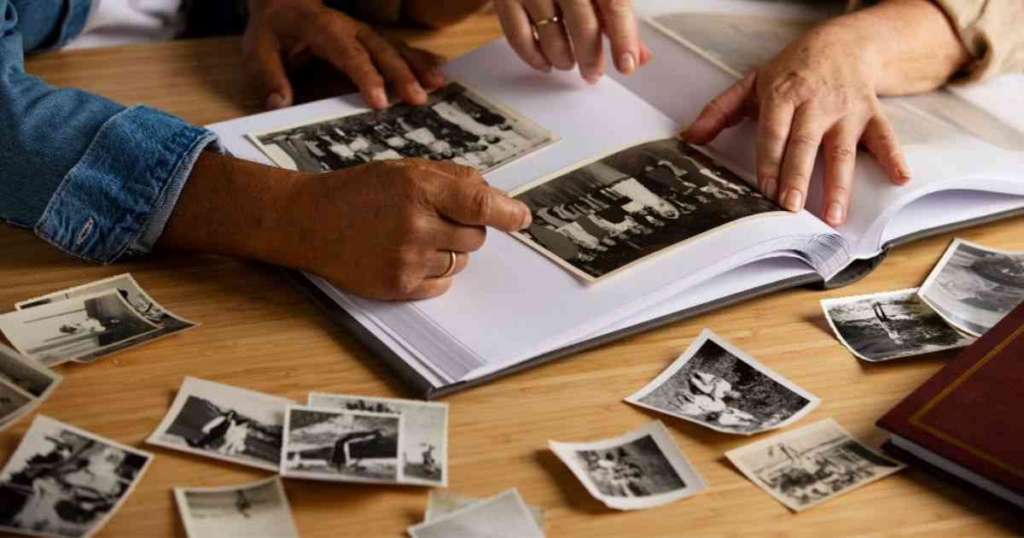
断片的に保存された記憶をその都度再編集する形をとっている。
ことのほか創造的なプロセスで、それゆえ記憶は実態とはそぐわず不正確になりやすい。
後知恵バイアスはその最たる例の1つなのだ。
結果に関する情報をいったん知ってしまうと、自分が結果を知る以前にどう状況を捉えていたかを思い出す際、その結果に関する情報が勝手になだれこんできてしまう。
そして一緒くたに再編集してしまうのだ。
さらに、その結果と辻褄が合うような記憶ばかりをえり好み(チェリーピッキングという名がある)して編集されがちとなる。

それゆえ、事前に考えていたことの記憶と直近の結果とが似通ってくる。
ますます最初から分かっていたと確信してしまうのだ。
アンカリング効果
「アンカリング」という別の認知バイアスが後知恵バイアスの原因の説明に使われることもある。
アンカリングとはもともと船の錨(いかり/anchor)から来ている言葉で、最初に提示された情報を無意識のうちに基準値とみなし、その後の判断が歪んでしまう傾向をいう。

たとえば「みりん」と10回言った後に「鼻の長い動物は?」と聞かれると、思わず「キリン」と答えてしまうといったことがその端的な例だ。
後知恵バイアスでも同様のアンカリングが一役買っている。
結果の情報をいったん知ってしまうと、その情報を基準値とみなし、結果を知る前に認識していたことを書き換えてしまうのだ。
後知恵バイアスと社会
後知恵バイアスと裁判
後知恵バイアスが日常のなにげない会話の中だけにとどまるだけならその罪は小さい。
「だったら最初にそういってよ」などと言い返して済む話しだろう。
しかし、後知恵バイアスが社会にとって好ましくない事象に発展し得ることも頭の中に入れておこう。
たとえば、後知恵バイアスが裁判の行方を左右してしまうこともあり得るのだ。
その1つが2012年に起きた水難事故の裁判である(産経新聞 2021.3.17)。

川に鉄砲水が発生し、遊んでいた幼稚園児が死亡するという痛ましい事故が起きた。
そして、引率した幼稚園教諭の過失を問えるかが裁判で争われたのだ。
最大の争点は鉄砲水の予兆である川の濁りを事前に察知でき、事故を回避することができたかどうかである。
検察側は事故前に撮影された川の写真は「濁って見えるため、鉄砲水は予見可能であった」と主張する。
一方の弁護側は「濁って見えるのは事故が起きた結末を知っているからそう見えるだけだ」と反論したという。
すなわち、弁護側の主張は検察側の見解は後知恵バイアスに過ぎず、引率者に予見はできなかったというものだった。
弁護側はそのことを裏付けるために、大学の研究チームに依頼し、懸案の川の写真が後知恵バイアスを引き起こし得ることを確かめている。
研究チームが行った実験では、実験参加者に水の濁りが鉄砲水の予兆になると伝えたうえで、写真に写った川の濁りの程度を7段階で判定してもらう。
ただし、参加者たちの半分には「実際に鉄砲水が起きた川」と結末を伝えてあり、残り半分の参加者には何も伝えなかった。
すると「結果」を事前に知らされたグループのほうが、濁りの程度をより高く判定したという。
同じ写真でも結果を知ることで濁りが強く見えるという典型的な後知恵バイアスが実証されたのだ。
後知恵バイアスと冤罪
この水難事故の裁判では弁護側が機転を利かせたことで後知恵バイアスを免れることができた。
しかし、実際は後知恵バイアスが誤判や冤(えん)罪の要因にもなっていると多くの識者が指摘している。
経験を積んだ裁判官や検察官でも例外ではなく、真相究明や正確な判断が阻害されてしまうのだ。

たとえば、後知恵バイアスが働くことで、取り調べする側が自らの思い込みに合致する証拠ばかりに注目する。
あるいは単なる偶然の一致を被疑者にむやみに関連付けてしまうといったことが往々にして起こり得る。
取り調べ中に、思い込みによる情報が繰り返し提示されることで、被疑者自身も感化され、実際に経験していないことを記憶してしまうことすらあるという。
後知恵バイアスと萎縮社会
後知恵バイアスによる誤った事実認定や不当判決がまかり通るようになると、人の命を預かる職業の人たちが訴訟リスクに怯(おび)えるようになる。
たとえば、医療の現場であればリスクの高い手術が避けられ、必要以上に検査を行うことが常態化する。
産婦人科など医療過誤の訴訟リスクが高いとされる診療科が敬遠され、深刻な医師不足や医師の偏在という別の問題も引き起こす。
後知恵バイアスは個人個人のちょっとした脳のクセに過ぎないが、社会の担い手となる人々を萎縮させてしまう。
社会全体に与える負の影響は決して小さくないのだ。
後知恵バイアスの対策
では後知恵バイアスを排するためにはどんな対策があるのだろうか?
以下の3つが考えられるだろう。
後知恵バイアスを知る
まずは後知恵バイアスが誰でも起こり得ることを認識することがその一歩だろう。
たとえ自分が専門家顔負けの知識やセミプロ級のスキルを持っている分野だったとしても例外ではない。
そのことを肝に銘じよう。
むしろそのような「自分は大丈夫」的な自負こそが柔軟な思考を妨げ、後知恵バイアスを誘発するのだと警戒するぐらいの覚悟が必要だ。
結果よりプロセスに意識を向ける
次に、事象や状況の結果だけに囚われるのではなく、その結果を招いたプロセスに意識を向けるようにする。
結果に至るまでにどんな情報が飛び交っていたのか?
それらの情報を見聞きして自分はどんな思索を巡らせていたのか?
結果に関する情報はいったん除外して冷静に思い返してみる。
すると「予見はできていた」という確信も実は怪しいことがわかってくる。
根拠が乏しく、結果を知ったことで錯覚していただけだったと気づき始めるようになるのだ。
感情に耳を澄ます
さらに一歩引いて、自分の内面にどんな感情が湧き上がっているのかを見つめ直すのもいいだろう。
感情が後知恵バイアスを助長することもあるからだ。
たとえば後悔や自責の念にひどく駆られていないか?
強引にでも自分を正当化しようとしていないか?
あるいは他者に対し優越感を得ようとしていないか?
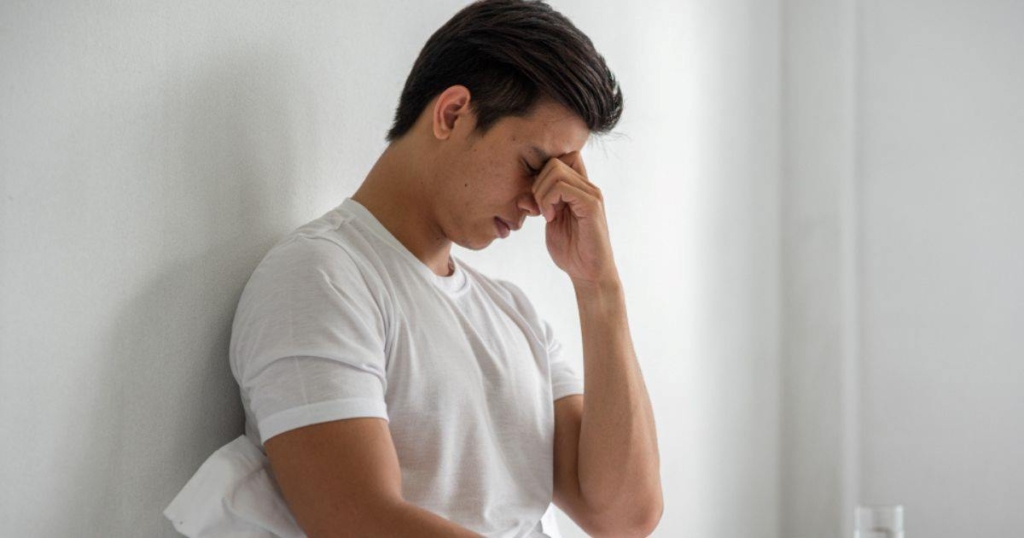


心の奥底の感情に耳を澄ましてみるのだ。
そんな感情の起伏に気づいたなら、後知恵バイアスに侵されやすくなっているといえる。
感情は早期警報システムとしても活用できると認識しよう。
決まり文句を禁句にする
とはいえ、識者の一致するところではあるが、後知恵バイアスを一網打尽にするのは難しい。
そこでひとまず、対策の射程を周囲の人たちから信頼を失わないことに絞ってみる。
後知恵バイアスにまつわる発言、口癖を言わないというルールをつくるのだ。
そうすることで、他人を責めてマウントを取っているという印象を与えずに済む。
あるいは自分を責めてばかりいることで、覚悟が足りず頼りない人とレッテルを貼られるのも避けられるだろう。
既に記事の前半でも触れているが、後知恵バイアス特有の「決まり文句」がある。
他者や自分に対して、それらが口を突いて出そうになったら意識的に口をつぐむように心がけるのだ。
そんな試みを助けるために、典型的な「後知恵バイアスフレーズ」をいくつか挙げておこう。
- ほら、やっぱり
- 言わんこっちゃない
- 最初からこうなるって分かってたよ
- やめときゃいいのにって思ってたよ
- だから言ったじゃないか!
- もっと慎重にやればよかったのに
- あんなことするからだよ
- いつかはやらかすと思っていた
- もっと早く相談してれればよかったのに
- 私の言うことを聞いていれば…
- もっと〇〇(例:勉強、下調べ)しておけばよかった
- なんであの時、ああしなかったんだろう
- もっと慎重に考えるべきだった
- ああ、もっと早く気づいていれば…
- あのとき、違う選択をしていたら…
貧困救済に生涯をささげ、ノーベル平和賞を受賞した故マザー・テレサは以下のような言葉を遺したという。
思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。
言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。
性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。
後知恵バイアスが手ごわく、思考に気をつけても克服できないなら、少なくとも自分の言葉を改めることから始めてみる。
その小さな試みが行動や習慣を変え、ひょっとすると自分の運命のみならず、人々が萎縮し、不寛容に向かいつつある社会を変えられるかもしれないのだ。


