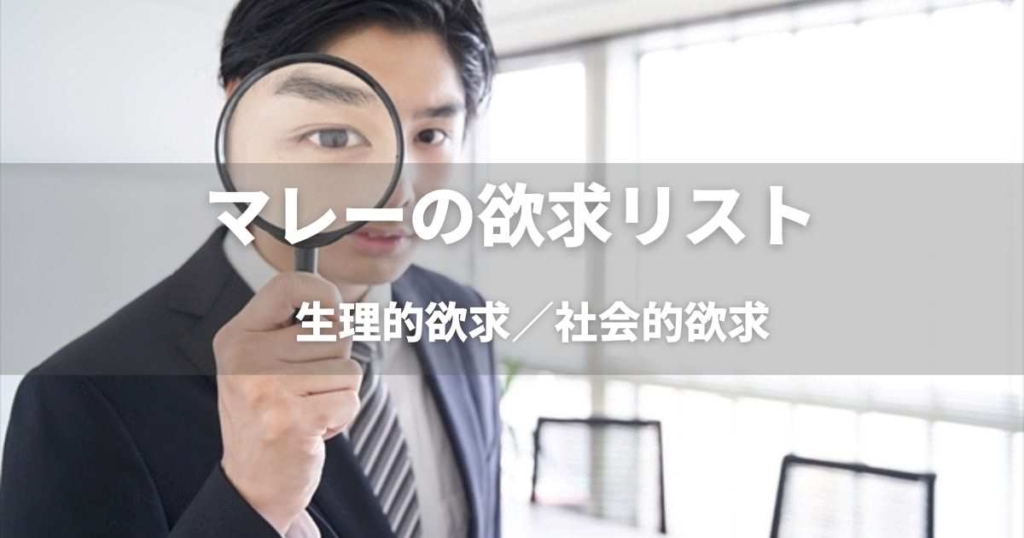心理法則– category –
-

身元のわかる犠牲者(被害者)効果:ひとりの死は悲劇、百万人の死は統計
「身元のわかる犠牲者効果」とは犠牲者が特定が可能な個人である場合に、そうでない場合と比べて、はるかに強い反応を人々が見せる傾向にあることをいう。 世界では毎日6,700人もの新生児が適切な治療を受けられず、救えるはずの命を落としていると聞いて... -

モラルライセンシング(モラル信任効果) その原因と対策とは?
「モラルライセンシング」とはよいことをすると悪いことをしたくなることをいう。 ちょっとした自制心や忍耐力を働かせる機会があると、「頑張った!」「いいことをした!」という自覚が生まれ、自分にご褒美をあげたくなる。 免罪符でももらったような気... -

計画錯誤と楽観バイアス その傾向と対策とは?
「計画錯誤」(プランニングの誤謬/計画の誤謬)とは何かの計画を立てる際、その遂行に要する時間や予算、労力などを少なく見積もってしまう傾向をいう。 つい楽観的な見通しを立ててしまうのだ。 それによって計画の進行が予定より大幅に遅れて締め切り... -

非注意性盲目と対策 日常の見落とし、マーケターに打つ手はあるか?
「非注意性盲目」とは視野に入っているのに、注意が向けられていないために見落とされてしまう現象をいう。 英語では「inattentional blindness」、とりわけ変化に気づかないなら「change blindness/チェンジ・ブラインドネス(変化盲)」といったりもす... -

人間の欲求59種類 マレーの欲求リスト進化版
人は誰もが59種類の社会的欲求を持つ。その唱えるのが2人の日本人心理学者による欲求体系だ。 米国の心理学者による「マレーの欲求リスト」(欲求一覧)に倣って開発されたという。 全59種と数が多く実務家には扱いにくいように思えるが、各欲求がわかり... -

マレーの欲求リスト 人間の欲求 最重要40種類とは?
欲求分類の先駆けともいえる「マレーの欲求リスト」(Murray's system of needs)。 全部で40種類もの欲求が名を連ね、その分類が非常に細やかで網羅的なのが特徴だ。 しかも一つひとつを見ていくと人の心の微細な機微をすくい上げており、消費者心理にま... -

好奇心 未知に挑む力 人間の欲求16種類(3)
好奇心とは「珍しい物事・未知の事柄に対して抱く興味や関心」のこと。 人は誰もが好奇心を持ち、未知の世界に足を踏み入れ、多くのことを学んでいる。 そして、この好奇心はマーケティングの世界にも生かされている。 情報の断片的開示にとどめ、あえて興... -

「独立」への欲求 人間の欲求16種類(2)
人は誰しもが生まれつき16の基本的欲求を持つ。 そして、それらの欲求は日常の何気ない判断や意思決定にも影響を与えている。 その16のうちの1つ、「独立」への欲求は人に頼らず自力でやりたいと望むこと。 歩き始めの子どもが親の手をつなぎたがらな... -

「力」の欲求 人間の欲求16種類(1)
人は誰しもが生まれつき16の基本的欲求を持つ。 そして、それらの欲求は日常の何気ない判断や意思決定にも影響を与えている。 その16のうちの1つ、「力」への欲求は周囲の人々に影響力を行使したいと望むこと。 スポーツ選手が「人々に感動を与えたい」... -

ERG理論と欲求5段階説の違いとは? マーケティング事例で解説
マーケターの間でもよく知られているのがマズローの「欲求5段階説」。 下位の「生理的欲求」から始まり、高次の「自己実現欲求」まで段階的に発動するという説だ。 大枠は似ているが、よりシンプルに3つの欲求に分かれるアルダファーの「ERG理論」と...