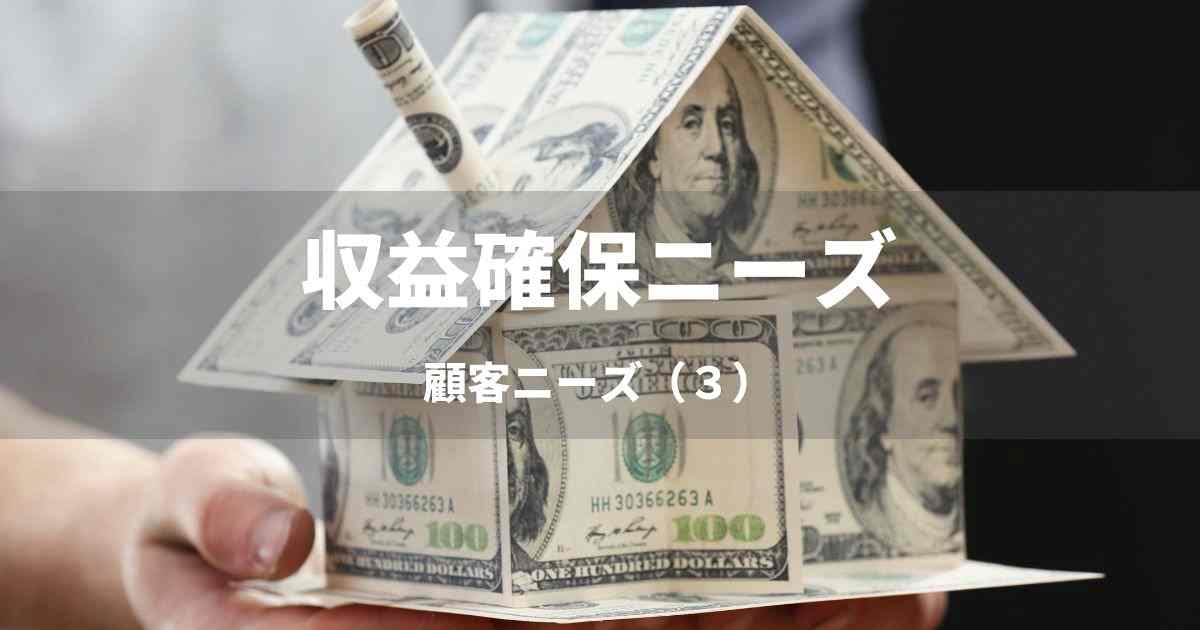本連載は、顧客が欲しいと思う30の価値要素を軸に、顧客ニーズの本質を深掘りしていく(ここでの顧客とは法人ではなく個人顧客のこと)。
今回は、機能的価値の中でも特に個人顧客の生活に直結する「収益確保(Makes money)」に焦点を当てる。
単に収入を増やすことを超え、個人顧客が収益確保によって本当に得たい「本質的な価値」とは何か。
本稿の後半では、「収益確保」ニーズが生まれる具体的な文脈を数多く例示している。
これは、マーケターの想像力を掻き立て、視野狭窄に陥らずにニーズを捉える多様な視点を培ってもらうためだ。
さらに、その「収益確保」ニーズを見事に捉え成功を収めた豊富な事例を紹介し、明日からの製品開発やマーケティング戦略に役立つ実践的なヒントも提供する。
個人顧客の「経済的目標を達成したい」という願いとは何たるかが、本稿から一通り掴みとれるはずだ。
経済的ゆとり/収入増/資産拡大/将来不安の解消/効率的なお金の増やし方/自己実現/投資の安心感/リスク低減/時間有効活用/賢い選択
第1章:導入 — 顧客の成功を追求する「収益確保」の価値
現代において、個人も持続的な成長と安定のために「収益確保」は不可欠な要素だ。
市場競争が激化し、経済状況が不安定さを増す中で、個人は単に良い製品やサービスを求めるだけでなく、それらを通じていかに自身の経済的利益を最大化できるかに注目している。
これは、個人が投資や副業、日々の消費において、より賢明な選択をし、具体的な成果を求めていることの表れといえる。
漠然とした「便利さ」や「快適さ」だけでなく、自身の財布に直結する「実利」を追求しているのである。

この「収益確保」という個人のニーズは、現代社会においてその重要性を増している。
製品やサービスを提供する側は、個人顧客がそれらを利用することで、どのように経済的なメリットを得られるのかを明確に提示する必要がある。
それは、提供する製品やサービスの機能面の説明に留まらず、顧客の投資対効果(ROI)や、将来的な資産形成、あるいは日々の生活における金銭的なゆとりにどう貢献するのかを示すことにつながる。
本連載は、マーケターが個人の潜在ニーズを掘り起こし、マーケティング戦略に活かすための羅針盤となるものである。
なかでも、本稿では「顧客が欲しいと思う30の価値要素」の中から、特に現代社会において重要性を増している「収益確保(Makes money)」に焦点を当てる。
このニーズがどのような文脈で生まれ、どのように個人の購買行動を後押しするのか、具体的な事例を交えながら深掘りしていく。
顧客ニーズ全般について深く理解するためには、まずはこちらの総括記事を参照してほしい。
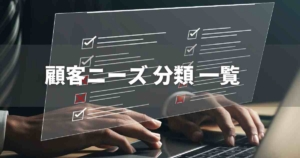
提供する商品やサービスが、個人顧客にとって「収益確保」の価値になっているか、そしてその価値が具体的に何を意味するのか。
次の章では、「収益確保」ニーズが持つ本質的な意味をさらに深く掘り下げていく。
第2章:「収益確保」ニーズの定義と顧客心理
「収益確保」とは何か?
「収益確保(Makes money)」ニーズとは、個人顧客が製品やサービスを利用することによって、直接的または間接的に自身の経済的利益を増大させたいという根源的な欲求である。
これは単に支出を抑えることに留まらず、投資収益率(ROI)の向上、新たな収入源の創出、資産価値の増加、あるいは副業やサイドビジネスを通じた所得の向上といった、具体的な経済的成果の追求を意味する。

現代社会において、個人は経済的な不確実性や競争の激化に直面している。
この状況下で、人々は自身の時間、労働、資本といったリソースを最大限に活用し、それに見合った、あるいはそれを上回る経済的なリターンを求めている傾向が強い。
この切実な「収益確保」への願望が、個人の購買行動を強く動機づける要因となる。
このニーズは、個人顧客が「何を得たいか」という側面から捉えることができる。
例えば、投資アドバイスサービスを通じて資産を増やしたい、副業で収入を得たい、あるいは日々の消費をより賢く行い、将来の資産形成につなげたい、といった具体的な目標がある。
したがって、「収益確保」ニーズを定義するならば、それは「個人顧客が自身の経済的状況を改善し、資産を増やし、あるいは所得を向上させるために、製品やサービスを通じて具体的な金銭的利益を得たいと望む欲求」である。
このニーズを満たすことは、個人の経済的自立を支援し、彼らの目標達成に直接貢献するため、非常に大きな価値を提供する。
顧客が「収益確保」を求める心理
個人顧客が「収益確保」を求める心理は多岐にわたるが、主に以下の要素が挙げられる。
- 経済的安定と安心感の追求
- 予測不可能な経済状況において、個人は将来への不安を軽減し、経済的な安定を確保したいと考える。収益の増加は、この安心感をもたらす。
- 目標達成への意欲
- 住宅購入や教育資金、老後資金の準備など、具体的な経済的目標の達成のために収益増加は不可欠である。個人は、その目標達成を加速させる手段を求めている。
- 生活水準の向上
- より良い住環境、質の高い教育、充実したレジャーなど、現在の生活水準を向上させるために、追加的な収益を求める心理がある。
- 自己実現と成功体験
- 自身の努力や投資が収益という具体的な成果となって現れることは、個人に大きな達成感と自己肯定感をもたらす。これは、単なる金銭的利益を超えた、精神的な充足感にもつながる。
- リソースの最適化
- 時間、労働力、資本といった限られたリソースを最大限に活用し、最大の収益を生み出したいという欲求がある。個人は、効率的な収益確保の手段を求めている。
これらの心理的要因を理解することは、「収益確保」を求める個人顧客の深い動機を捉え、真に価値ある製品やサービスを提供する上で不可欠である。
第3章:「収益確保」ニーズが発生する具体的な文脈例
「収益確保」ニーズは、個人の経済活動のあらゆる局面に深く根差している。
単に所得を増やしたいというだけでなく、その背景には「もっと効率的に稼ぎたい」「リスクを抑えて資産を増やしたい」「将来への経済的不安を解消したい」という強い思いが存在する。
ここでは、マーケターがこのニーズをより具体的に捉えやすいよう、具体的な文脈例を挙げる。
「収益確保」ニーズが発生しやすい条件
個人顧客が「収益確保」を強く意識する瞬間は、特定の状況下で顕著になる。
以下に、その代表的な条件を列挙する。
- 経済的な不確実性や先行きの不安に直面したとき:
- 景気後退、インフレ、不安定な雇用情勢など、将来への経済的な見通しが不透明な状況下で、自身の資産を守り、増やしたいという欲求が高まる。
- 既存の収入源に限界や課題を感じるとき:
- 本業の収入だけでは不十分だと感じたり、昇給が見込めなかったりする際に、新たな収益源の確保や所得の向上を模索する。
- 投資機会を探しているとき:
- 預貯金だけでは資産が増えないと感じたり、より高いリターンを期待できる投資先を探したりする際に、適切な投資アドバイスやツールへのニーズが発生する。
- 時間や労力を効率的に収益に結びつけたいとき:
- 副業やサイドビジネスを始めたいが時間がない、あるいは本業の時間を削らずに収入を増やしたいと考える際に、効率的な収益化手段や自動化ツールへの関心が高まる。
- 特定の目標達成のために資金が必要なとき:
- 住宅購入、子どもの教育費、老後資金、旅行など、具体的な目標達成のためにまとまった資金を増やしたいと考えるときに、収益確保への意識が高まる。
- 余剰資産や遊休資産を有効活用したいとき:
- 使っていない不動産やスキル、空き時間などを収益に変えたいと考える際に、シェアリングエコノミーやマッチングサービスに目を向ける。
上記に挙げた条件は、個人顧客が「収益確保」の重要性を認識し、具体的な行動を検討し始めるきっかけとなる。
これらの背景にある心理を理解することで、マーケターは顧客が抱える漠然としたニーズの根源を捉えることができるだろう。
次のセクションでは、これらの条件がどのように具体的な購買行動やサービス利用の文脈へと繋がるのか、さらに詳細な具体的な文脈事例を提示する。
「収益確保」ニーズが発生する具体的文脈
「収益確保」ニーズは、日々の生活の中で様々な形で顔を出す。
ここでは、個人顧客が具体的にどのような状況で、何を「収益確保」したいと願うのか、そのリアルな行動や感情に焦点を当てて例示する。
顧客の心に響く製品やサービスを創出するための洞察を得る一助となるだろう。
- 資産運用を始めたい・見直したいとき:
- NISAやiDeCoなど、非課税制度を活用して効率的に資産形成したい。
- 投資信託や株式投資で、より高い利回りを追求したいが、何から始めてよいか分からない。
- 不動産投資に興味があるが、リスクを抑えつつ安定した家賃収入を得る方法を知りたい。
- 副業やサイドビジネスで収入を得たいとき:
- 本業の傍ら、空き時間を利用してクラウドソーシングでスキルを活かしたい。
- フリマアプリで不要品を売却して現金化したい。
- ブログやSNSを通じてアフィリエイト収入を得たいが、効果的なノウハウを知りたい。
- 自身のスキルや知識を収益化したいとき:
- オンライン講座を開設して専門知識を販売したい。
- コンサルティングサービスを提供して、顧客の課題解決を支援したい。
- クリエイターとして、自身の作品を販売するプラットフォームを探している。
- 日々の消費で賢くお金を増やしたいとき:
- ポイント還元率の高いクレジットカードやキャッシュレス決済を利用し、支出から効率的にポイントを獲得したい。
- 家計簿アプリで支出を管理し、無駄を削減して貯蓄を増やしたい。
- 株主優待やふるさと納税などを活用し、実質的な所得を増やしたい。
- 遊休資産やスペースを収益に転換したいとき:
- 自宅の空き部屋を民泊として貸し出し、副収入を得たい。
- 使っていない駐車場をシェアリングサービスで貸したい。
- 使わなくなった車をカーシェアサービスで貸し出し、維持費をカバーしたい。
次の章では、実際に「収益確保」ニーズを見事に捉え、成功を収めている具体的な事例を深掘りしていく。
第4章:「収益確保」ニーズを満たす成功事例
「収益確保」ニーズを満たす製品やサービスは、個人顧客の経済的目標達成を直接的に支援し、具体的な金銭的メリットを提供することで、高い評価と支持を得ている。
ここでは、様々な業界における具体的な成功事例を挙げ、その「収益確保」の仕組みと、個人顧客に提供する価値を深掘りする。
事例1:高利回り投資型クラウドファンディング
収益確保の仕組み
不動産や再生可能エネルギーなど、これまで個人投資家がアクセスしにくかった高利回りの投資案件に、少額から参加できるプラットフォームを提供する。
複数の投資家の資金をまとめ、大規模なプロジェクトに投資することで、個別では得られない収益機会を創出する。
運用のプロが案件を選定し、分配金を定期的に投資家に支払う仕組みである。
顧客への価値
預貯金では得られない高利回りを期待でき、資産形成のスピードを加速できる。
専門的な知識や多額の資金がなくても、多様な投資案件に手軽に分散投資できるため、リスクを抑えながら収益機会を追求できる。
事例2:成果報酬型アフィリエイトプラットフォーム
収益確保の仕組み
ブロガーやインフルエンサーが自身のウェブサイトやSNSを通じて企業の商品・サービスを紹介し、その紹介から発生した売上や登録に応じて報酬を得られる仕組みを提供する。
プラットフォームが企業とアフィリエイターを仲介し、報酬の管理や支払いを自動化するため、双方が効率的に収益を上げられる。
顧客への価値
自身のメディアや影響力を活用し、新たな収益源を構築できる。
専門的な営業スキルがなくても、興味のある分野の商品を紹介するだけで副収入を得られるため、個人の収益最大化に貢献する。
事例3:AI搭載型自動家計簿・資産管理アプリ
収益確保の仕組み
銀行口座やクレジットカード、証券口座など複数の金融機関のデータを連携し、個人の収支や資産状況を自動で可視化・分析する。
AIが支出の無駄を特定し、節約のアドバイスを提案したり、資産運用のポートフォリオ最適化を支援したりすることで、個人の貯蓄率向上や資産増加に寄与する。
顧客への価値
煩雑な家計管理の手間を大幅に削減しながら、自身の「お金の流れ」を正確に把握し、無駄な支出を効率的に減らせる。
これにより、手元に残るお金が増え、将来の資産形成や投資に回せる資金を増やし、経済的なゆとりと安心感を得られる。
事例4:スキルシェアリング・ギグワークプラットフォーム
収益確保の仕組み
個人の持つ特定のスキル(例:プログラミング、デザイン、語学、コンサルティングなど)を必要とする企業や個人とマッチングする場を提供する。
個人顧客は、自身の専門知識や空き時間を活用して単発の仕事を受注し、対価を得られる。プラットフォームが契約、決済、評価システムを整備し、安全な取引を促進する。
顧客への価値
本業以外の時間を有効活用して追加収入を得られる。
自身のスキルや経験を直接収益に結びつけることができ、場所や時間に縛られない柔軟な働き方を実現することで、個人の経済的自立を支援する。
事例5:投資信託・ロボアドバイザーサービス
収益確保の仕組み
個人のリスク許容度や投資目標に合わせて、AIが最適な資産配分を提案し、自動で運用を行うサービスである。
世界中の多様な資産(株式、債券、不動産など)に分散投資することで、リスクを抑えながら安定的なリターンを目指す。積立投資機能も備え、長期的な資産形成を支援する。
顧客への価値
投資の専門知識がなくても、手軽に分散投資を始められ、プロレベルの資産運用を実践できる。
感情に左右されない自動運用により、市場の変動に一喜一憂することなく、着実に資産を増やしていくことが期待できる。
事例6:高還元率ポイントプログラム・キャッシュバックサービス
収益確保の仕組み
クレジットカード利用や特定店舗での購買、オンラインサービスの利用などに応じて、高い還元率でポイントやキャッシュバックを提供する。
貯まったポイントは現金同等で利用できたり、電子マネーに交換できたりするため、実質的な支出を抑え、可処分所得を増やせる。
顧客への価値
日々の消費活動を通じて、意識せずに「お金が貯まる」感覚を得られる。
生活費の一部が実質的に削減されるため、経済的なゆとりが生まれ、その分を貯蓄や他の消費に回すことが可能になる。
事例7:遊休資産活用型シェアリングサービス(例:駐車場シェア)
収益確保の仕組み
個人が所有する使っていない駐車場や空きスペースを、必要な時に他者に貸し出すことができるプラットフォームを提供する。
スマートフォンアプリで簡単に貸し出し・予約・決済が行えるため、個人は手軽に遊休資産を収益化できる。
顧客への価値
利用されていない資産から手軽に副収入を得られる。
初期投資なしで始められ、管理の手間も少ないため、個人の隙間時間や資産を有効活用し、経済的なメリットを享受できる。
これらの事例は、「収益確保」という個人顧客のニーズが、多様な形で実現され、具体的な経済的メリットを提供していることを示している。
単に機能を提供するだけでなく、個人顧客がどのように金銭的な価値を得られるのかを明確に提示することが、製品やサービスの成功には不可欠である。
次の章では、これまでの考察を踏まえ、「収益」がいかに個人の目標達成と持続的な成長の源泉となるかについて総括する。
第5章:総括——「収益」は、個人の「目標」と「成長」の源泉
これまでの議論を通じて、「収益確保(Makes money)」というニーズが、単に所得を増やすことや資産を増やすことにとどまらない、個人顧客の根源的な欲求であることが明らかになったであろう。
個人は、経済的な不安や将来への不確実性から解放され、その分を自分にとって本質的な価値、例えば夢の実現、生活水準の向上、精神的なゆとりといった「本当に求めていること」に意識とエネルギーを向けたいと願っているのだ。

マーケターは、この「収益確保」ニーズを深く理解し、自社の商品やサービスが個人顧客のどのような経済的課題を解決できるのか、そしてその結果としてどのような「経済的安定」や「目標達成の加速」、「新たなゆとり」を提供できるのかを明確にすることが重要である。
たとえば、
- 個人顧客がリスクや不確実性を感じる投資において、どう安心感を提供できるか?
- 個人顧客がスキルや時間を収益に結びつけたいと願う状況で、どう最適な機会を提示できるか?
- 個人顧客が賢くお金を増やしたいと願う体験のために、どう効率的なツールや情報を提供できるか?
といった問いを常に持ち続ける必要があるだろう。
「収益確保」は、単なる機能的価値ではなく、個人の経済的負担の軽減や、生活の質(QOL)向上に直結する感情的価値も内包している。
提供する製品やサービスが、個人顧客にとって「経済的な目標達成を共に目指すパートナー」となるとき、それは単なる消費財を超え、顧客の心に深く響く存在となるであろう。