多数派に流されるか、少数派に肩入れするか——その選択には、知られざる心理メカニズムが働いている。
本稿では、バンドワゴン効果とアンダードッグ効果の違いを軸に、「選好の外部性」という経済的視点から意思決定の構造を読み解く。
マーケティングや選挙戦略への応用事例も交え、ビジネスパーソンの思考に役立つ視点を提示する。
1.なぜ今「バンドワゴン効果」に注目するのか?
「多くの人が選んでいるから、自分もそれに従うべきだ」——このような心理は、現代の意思決定において無視できない影響力を持っている。
選挙、商品選び、SNSのトレンドなど、あらゆる場面で他者の選好が自分の判断に波及する現象が見られる。
言い換えれば、個人の選択が、周囲の選択によって左右されるという構造である。

これは経済学的には「選好の外部性」と呼ばれるものであり、情報が過剰に流通する現代において、その重要性はますます高まっている。
その代表的な例が「バンドワゴン効果」である。
多数派に同調することで安心感や正当性を得ようとするこの傾向は、マーケティングや政治戦略においても活用されている。
一方で、劣勢にある対象に対して共感や応援の気持ちが集まる「アンダードッグ効果」も、逆のベクトルで人々の行動を左右する。
本稿では、これら二つの心理効果を比較しながら、現代の意思決定に潜むメカニズムを読み解いていく。
2.バンドワゴン効果とは何か
バンドワゴン効果とは、多くの人が支持している対象に対して、さらに支持が集まる現象を指す。
いわば「勝ち馬に乗る」心理であり、他者の選択が自分の選好に影響を与える典型的な例である。
この効果の語源は、選挙キャンペーンで使用された「バンドワゴン(楽隊車両)」に由来する。
支持者を次々と乗せていく様子が、まるで人気の波に乗るような構図であったことから、この名称が定着した。
実際の場面では、選挙報道で「優勢」とされた候補者に票が集中するケースがある。
これは、有権者が「多数派に属すること」や「勝ちそうな側に加わること」に安心感や合理性を見出すためである。
同様の傾向は、商品選びやトレンド消費にも見られる。
たとえば「売上ランキング1位」「○万人が購入」などの表示は、バンドワゴン効果を意図的に活用したマーケティング手法である。
この効果は、個人の選好が他者の選好に依存する「選好の外部性」の一種であり、特に情報が可視化されやすい現代社会において、その影響力は増している。
多数派の支持がさらなる支持を呼ぶという構造は、社会的証明(多数派の行動が、正しさや妥当性の証拠とみなされる現象)や同調圧力とも密接に関係している。
3.アンダードッグ効果とは何か
アンダードッグ効果とは、劣勢にある人物や組織、商品などに対して、同情や応援の気持ちが高まり、結果として支持が集まる現象を指す。

日本語で言う「判官びいき」に近い心理であり、バンドワゴン効果とは対照的な選好の動きである。
この効果は、選挙やスポーツの場面で顕著に現れる。
たとえば、事前の世論調査で劣勢とされた候補者が、選挙当日に予想外の票を獲得するケースがある。
これは、有権者が「不利な状況でも頑張っている姿」に共感し、応援の気持ちから投票行動を変化させるためである。
マーケティングの文脈でも、アンダードッグ効果は活用されている。
スタートアップ企業が「資金や知名度に恵まれずとも、独自の価値を信じて挑戦を続ける」といった物語を語ることで、消費者の共感を呼び、支持を集めるケースは多い。
クラウドファンディングやSNS上の応援文化も、この効果の延長線上にある。
アンダードッグ効果は、選好の外部性の一種であるが、バンドワゴン効果とは異なり「他者の支持が少ないこと」がむしろ支持の動機となる点が特徴的である。
つまり、多数派に属することよりも、「少数派を応援すること」に価値を見出す心理が働いている。
4.両者の違いと共通点
バンドワゴン効果とアンダードッグ効果は、一見すると正反対の現象である。
しかし、いずれも他者の選好や状況に影響されて自らの判断を変えるという点で、共通の心理的メカニズムに根ざしている。
両者の違いは、支持の集まり方にある。
バンドワゴン効果は「多数派への同調」によって支持が拡大する。
一方、アンダードッグ効果は「少数派への共感」によって支持が集まる。
前者は安心感や合理性を求める行動であり、後者は情緒的な応援や逆転への期待が動機となる。
以下に、両者の特徴を簡潔に比較する。
| 比較項目 | バンドワゴン効果 | アンダードッグ効果 |
|---|---|---|
| 支持の方向性 | 優勢な対象に集まる | 劣勢な対象に集まる |
| 心理的動機 | 多数派への同調、安心感 | 弱者への共感、応援したい気持ち |
| 社会的影響 | 流行や人気の加速 | 逆転劇や支持の再分配 |
| 典型的な事例 | 人気政党への投票、売上ランキング上位 | 劣勢候補への支援、挑戦者ブランドの応援 |
両者は、他者の選好が自分の選好に影響を与えるという点で共通しており、こうした構造は経済学では「選好の外部性」と呼ばれる。
この概念については、次章で詳しく取り上げる。
5.「選好の外部性」とは何か
選好の外部性とは、ある個人の選好(好みや選択)が、他者の選好に影響を与える現象を指す。
経済学や行動科学の分野で用いられる概念であり、個人の意思決定が孤立して行われるのではなく、社会的な文脈の中で相互に作用し合うことを示している。
この外部性には、主に二つの方向性がある。
ひとつは「正の選好外部性」であり、他者がある対象を好むことで、自分もそれを好むようになる傾向を指す。
バンドワゴン効果はこの典型であり、多数派の支持がさらなる支持を呼ぶ構造になっている。
もうひとつは「負の選好外部性」である。
他者がある対象を好んでいることが、自分の選好を抑制する、あるいは逆方向に働く傾向を指す。
アンダードッグ効果はこのタイプに該当し、他者の支持が少ない対象に対して、むしろ自分が支持したくなる心理が働く。
なお、負の選好外部性の一例として「スノッブ効果(snob effect)」も挙げられる。
他者が好むものをあえて避けることで、自分の独自性や差別化を保とうとする心理であり、特に高級品や限定品の消費行動において見られる。
アンダードッグ効果が共感や応援の感情に基づくのに対し、スノッブ効果は差異化や優越感を動機とする点で異なる。
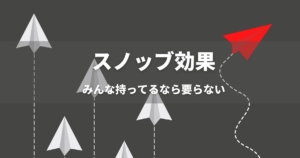
選好の外部性は、マーケティングや政治戦略において極めて重要な概念である。
たとえば、人気商品の「売れている」という情報は、消費者の選好を誘導する力を持つ。
一方で、挑戦者ブランドが「まだ知られていないが、価値がある」と訴えることで、共感を呼び起こす戦略も成立する。
このように、選好の外部性を理解することは、個人の意思決定だけでなく、集団の行動や市場の動向を読み解く上でも有効である。
バンドワゴン効果とアンダードッグ効果は、その両極に位置する現象として、選好のダイナミズムを象徴している。
6.応用と示唆:マーケティング・政治・文化への影響
マーケティングにおける「人気の可視化」と共感設計
バンドワゴン効果とアンダードッグ効果は、単なる心理現象にとどまらず、実務の現場においても戦略的に活用されている。
とりわけマーケティング、政治、文化の領域では、これらの効果を意識した設計が成果に直結することが多い。
マーケティングにおいては、バンドワゴン効果を利用した「人気の可視化」が定番の手法である。
「売上ランキング1位」「○万人が購入」「レビュー高評価」などの表示は、消費者に安心感と信頼感を与え、購買行動を促進する。
クラウドファンディングでは、達成率が6割を超えた瞬間に支援が加速し、「すでに800人が支援」の表示がさらなる支援を呼び込む。
AppleのAirPodsは、白いイヤホンを街中で目立たせることで「みんな使っている」という印象を拡散させた。
ワインショップでは、棚に数本しか残っていないボトルほど「人気がある」と判断されやすく、レストランでは窓際の席に客を配置することで通行人に繁盛感を演出し、来店を促す。
これらはすべて、他者の選好が自分の選好に影響する「選好の外部性」を前提とした設計である。
一方、アンダードッグ効果は、挑戦者ブランドやスタートアップ企業の訴求において有効である。
「資金も知名度もないが、情熱と革新性で勝負する」といったストーリーは、消費者の共感を呼び、応援という形で支持を集める。
クラフトビール醸造所が「不器用すぎてごめんなさい」と失敗作を公開したところ、応援購入が殺到した事例や、スタートアップが倒産寸前の再挑戦ストーリーで投資を獲得した事例はその典型である。
古典的な広告・ブランド戦略の例としては、レンタカー業界のAvisが挙げられる。「私たちは業界2位に過ぎません。だから、もっと努力します(We try harder)」」というコピーで、自らの劣位を武器に変え、市場シェアを大きく伸ばした。
また、自動車ブランド再生の事例としては、チェコの自動車メーカーŠkoda(シュコダ)がある。
「これはシュコダです」と過去の悪評を逆手に取り、品質向上とともにブランド再生を果たした。
かつて“乗りたくない車”の代名詞だった同社は、正面から弱点を認めることで、信頼と驚きを獲得したのである。
選挙戦略と報道の演出
政治の分野でも、バンドワゴン効果とアンダードッグ効果は選挙戦略に活用されている。
優勢を強調することで支持を広げる手法はバンドワゴン効果に基づき、逆に「劣勢でも信念を貫く候補者」として共感を誘う戦略はアンダードッグ効果を狙ったものだ。
報道の仕方や世論調査のタイミングも、こうした心理に影響を与える。
選挙期間中に「勢いがある」と報じられれば票が集まり、逆に「苦戦中」と伝えられることで応援の気持ちが高まることもある。
選挙の支持形成は、政策や実績だけでなく、「空気」や「物語」によっても左右される。
両効果は、政治的選好の裏にある見えにくい力学を映し出している。
流行と少数派支持の文化的構造
文化的な側面では、流行やムーブメントの形成にバンドワゴン効果が働く一方で、ニッチな価値観や少数派の声に光を当てるアンダードッグ的な支持も存在する。
多数派と少数派の間で揺れ動く選好のダイナミズムは、現代社会の多様性と共感構造を映し出している。
このように、両効果を理解し、適切に活用することは、単なる知識の習得にとどまらず、実践的な戦略構築においても有効である。
選好の外部性を前提とした設計は、現代の情報環境においてますます重要性を増している。
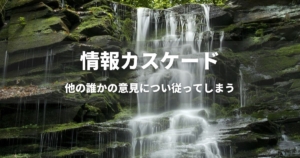
7.まとめ:人はなぜ“勝ち馬”に乗るのか、なぜ“負け犬”を応援するのか
人は意思決定において、合理性だけでなく、社会的な文脈や感情の影響を強く受ける。
バンドワゴン効果は、多数派に属することで安心感や正当性を得ようとする心理の表れであり、アンダードッグ効果は、劣勢な対象に対して共感や応援の気持ちを抱く人間らしい感情の反映である。
両者は対照的な動機に基づいているが、いずれも「選好の外部性」という共通の構造を持つ。
他者の選好が自分の選好に影響を与えるという点において、現代の情報環境ではその力が一層強まっている。
この二つの効果を理解することは、マーケティングや政治、文化の設計において有益であるだけでなく、自身の意思決定を客観的に見つめ直す手がかりにもなる。
多数派に流されるのか、少数派に肩入れするのか——その選択の背景には、私たち自身の価値観が映し出されている。

