本連載は、顧客が欲しいと思う30の価値要素を軸に、顧客ニーズの本質を深掘りしていく。
ここでの顧客とは、法人ではなく個人顧客を指す。
今回は、機能的価値の中でも特に現代社会において重要性を増している「つなぐ(Connects)」に焦点を当てる。
単に人々やモノを物理的・仮想的に結びつけることを超え、個人顧客が「つながり」によって本当に得たい「本質的な価値」とは何か。
本稿の後半では、「つなぐ」ニーズが生まれる具体的な文脈を数多く例示している。
これは、マーケターの想像力を掻き立て、視野狭窄に陥らずにニーズを捉える多様な視点を培ってもらうためである。
さらに、その「つなぐ」ニーズを見事に捉え、成功を収めた豊富な事例を紹介し、明日からの製品開発やマーケティング戦略に役立つ実践的なヒントも提供する。
個人顧客の「孤立感を解消し、より豊かで意味のあるつながりを得たい」という願いとは何たるかが、本稿から一通り掴みとれるはずだ。
孤独感の解消/安心感/共感/新たな出会い/コミュニティ形成/情報共有/心理的充足/体験の共有/心の距離/安全確保
第1章:導入 — 顧客の「孤立」を解消する「つなぐ」の価値
現代社会は、テクノロジーの進化と共に、我々の生活に多くの利便性をもたらしている。
一方で、我々は物理的な距離や時間の制約、情報過多といった要因によって、時に「孤立」を感じることも少なくない。
インターネットが普及し、スマートフォンの登場で誰もが簡単に世界と繋がれるようになったはずなのに、なぜか満たされない孤独感や、大切な人との心の距離を感じることもあるだろう。
このような状況下で、顧客は単に個々の便利な製品やサービスを求めるだけでなく、それらがいかに人と人、または人とモノを物理的・仮想的に結びつけ、コミュニケーションや連携を可能にするかに注目している。
これは、個人が日々の生活において、より豊かな人間関係や、効率的な情報共有、あるいは安心感を得たいと願っていることの表れといえる。
漠然とした「便利さ」や「機能性」だけでなく、自身の精神的な充足や生活の質の向上に直結する「つながり」を追求しているのだ。
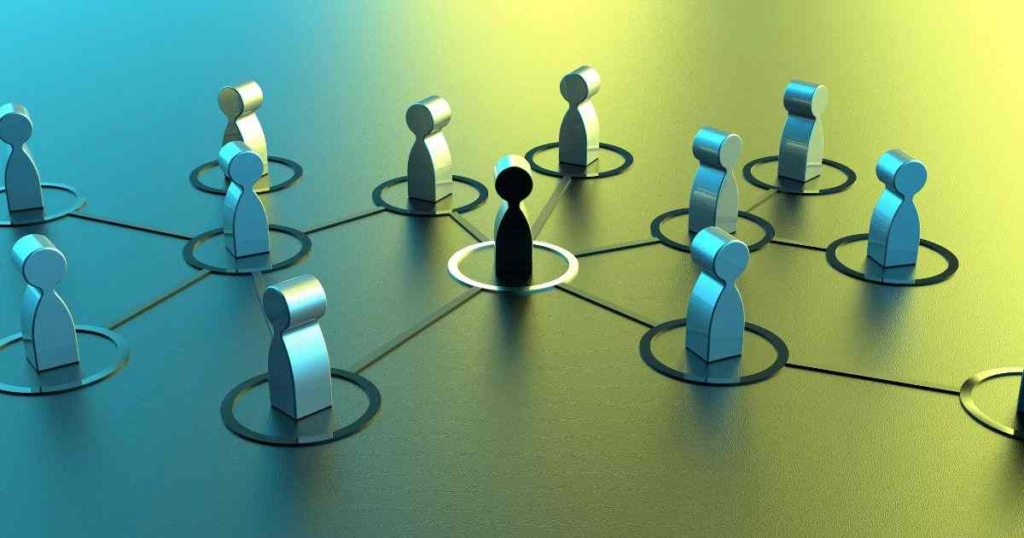
この「つなぐ(Connects)」という個人のニーズは、現代社会においてその重要性を増している。
製品やサービスを提供する側は、個人顧客がそれらを利用することで、どのように潜在的な孤立や断絶を解消できるのかを明確に提示する必要がある。
それは、提供する製品やサービスの機能面の説明に留まらず、顧客が抱える孤独感や情報格差への懸念をどう解消し、将来的な「共感」や「新たな体験の創造」にどう貢献するのかを示すことにつながる。
本連載は、マーケターが個人の潜在ニーズを掘り起こし、マーケティング戦略に活かすための羅針盤となるものである。
なかでも、本稿では「顧客が欲しいと思う30の価値要素」の中から、特に現代社会において重要性を増している「つなぐ(Connects)」に焦点を当てる。
このニーズがどのような文脈で生まれ、どのように個人の購買行動を後押しするのか、具体的な事例を交えながら深掘りしていく。
顧客ニーズ全般について深く理解するためには、まずはこちらの総括記事を参照してほしい。
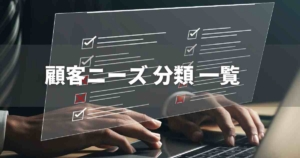
提供する商品やサービスが、個人顧客にとって「つなぐ(Connects)」の価値になっているか、そしてその価値が具体的に何を意味するのか。
次の章では、「つなぐ(Connects)」ニーズが持つ本質的な意味をさらに深く掘り下げていく。
第2章:「つなぐ」ニーズの定義と顧客心理
「つなぐ」とは何か?
「つなぐ(Connects)」ニーズとは、個人顧客が製品やサービスを利用することによって、人々と人、または物と物を物理的・仮想的に結びつけ、コミュニケーションや連携を可能にすることで、精神的な充足、情報共有の促進、あるいは安心感を最大化したいという根源的な欲求である。
これは単に複数の要素を結合することに留まらない。
物理的な距離、時間の制約、情報格差、あるいは心の壁といった「分断」によって生じる孤独感や不便さを解消し、より豊かで意味のある「つながり」を求めることを意味する。
現代社会において、個人は多様な情報ツールやコミュニケーション手段に囲まれている。
この状況下で、人々は自身の人間関係や情報環境が、断絶されずに円滑に機能し、温かい「きずな」を確保したいと強く願う傾向がある。
この切実な「つながり」への願望が、個人の購買行動を強く動機づける要因となるのだ。
このニーズは、個人顧客が「誰と、何を、どのように繋ぎたいか」「何が繋がることで価値が生まれるか」という側面から捉えることができる。
例えば、遠く離れた家族とリアルタイムで会話したい、共通の趣味を持つ人々と交流したい、あるいはスマートデバイスを連携させて安心感を高めたい、といった具体的な目標がある。

したがって、「つなぐ(Connects)」ニーズを定義するならば、それは「個人顧客が自身の人間関係、あるいは物理的・仮想的な環境における孤立や断絶を解消し、より連携的で包括的な状態を実現したいと望む欲求」である。
製品やサービスを通じて具体的なコミュニケーションや安心感、新たな体験を得たい、という顧客の願いを叶えるものなのだ。
このニーズを満たすことは、個人の孤独感への負担を解消し、彼らのより充実した社会生活の実現に直接貢献するため、非常に大きな価値を提供する。
顧客が「つなぐ」を求める心理
個人顧客が「つなぐ」を求める心理は多岐にわたるが、主に以下の要素が挙げられる。
- 孤独感からの解放と安心感の獲得
- 現代社会において、多くの人が孤独を感じている。物理的に離れていたり、社会との接点が少なかったりすることで生まれる孤立感を解消したいという欲求は根深い。
- 「つなぐ」機能は、友人や家族との距離を縮め、社会との接点を提供することで、顧客に安心感と心のゆとりをもたらす。
- 情報共有と相互理解の促進
- 人は、自分の考えや感情を他者と共有し、理解し合いたいと願う。「つなぐ」ことで、遠隔地の人とリアルタイムで情報を共有したり、共通の話題で盛り上がったりすることが可能になる。
- これにより、顧客は自身の意見が尊重され、他者と深くつながっている感覚を得られる。
- 新たなコミュニティ形成と所属欲求の充足
- 共通の興味や趣味を持つ人々とつながり、新しいコミュニティに所属したいという欲求は、人間の根源的な欲求の一つである。
- 「つなぐ」機能は、オンラインゲームやSNS、フォーラムなどを通じて、見知らぬ人とも繋がり、新たな仲間を見つける場を提供する。これは、顧客の承認欲求や所属欲求を満たすことにつながる。
- 利便性の向上と効率的な連携
- 物理的なモノ同士が「つながる」ことで、顧客の生活の利便性が向上する。
- 例えば、スマートホームデバイスが連携することで、照明やエアコンの操作が自動化されたり、見守りカメラが離れた家族の様子を伝えてくれたりするなど、個々のモノが連携することで、単体では得られない効率性や新たな体験が生まれる。
- 承認欲求と自己表現の場
- SNSなど「人々と人をつなぐ」プラットフォームは、自己表現の場としても機能する。自身の活動や考えを発信し、他者から「いいね」やコメントを得ることで、承認欲求が満たされる。
- また、他者の反応を通じて、自身の存在価値を確認できることも、このニーズを満たす重要な要素である。
これらの心理的要因を理解することは、「つなぐ」を求める個人顧客の深い動機を捉え、真に価値ある製品やサービスを提供する上で不可欠である。
第3章:「つなぐ」ニーズが発生する具体的な文脈例
「つなぐ(Connects)」ニーズは、個人の日常生活における人間関係、情報共有、エンターテイメント、さらには安全や安心の確保において、ますます重要性を増している。
単に個々の製品やサービスを使いたいというだけでなく、その背景には「もっと大切な人と近くにいたい」「新しい人々と出会いたい」「同じ趣味を共有する仲間と語り合いたい」「離れた家族の安否を確認したい」という強い思いが存在する。

ここでは、マーケターがこのニーズをより具体的に捉えやすいよう、網羅的かつ体系性に優れた豊富な文脈例を挙げる。
離れた人とのコミュニケーションが困難なとき
- 物理的な距離による隔たりがある場合:
- 単身赴任中の夫と家族が、普段の生活の様子を共有したい。
- 遠く離れて暮らす高齢の親と、頻繁に顔を見て話したい。
- 留学中の子どもと、日本の友人が気軽に連絡を取り合いたい。
- 災害時や緊急時に、家族や友人の安否を素早く確認したい。
- 時間の制約により顔を合わせられない場合:
- 仕事が忙しく、友人や同僚と予定が合わず、なかなか会えない。
- 子育て中で外出が難しく、ママ友と情報交換をしたい。
- 夜勤のため、日中にしか活動しない友人との交流が難しい。
新しい人間関係を築きたいとき
- 共通の趣味や関心を持つ仲間を見つけたい場合:
- 同じゲームをプレイしている人と、戦略を共有したり一緒にプレイしたりしたい。
- 特定のアーティストのファン同士で、イベント情報を交換したり感想を語り合ったりしたい。
- ニッチな趣味(例:登山、釣り、ボードゲームなど)について語り合える仲間を探したい。
- 恋愛や結婚につながる出会いを求めている場合:
- 日常の生活圏では出会いがなく、新しい異性と知り合いたい。
- 共通の価値観を持つ相手と真剣な交際を検討したい。
- スキルアップやキャリア形成のための人脈を広げたい場合:
- 特定の業界の専門家とつながり、知識や情報を得たい。
- キャリアアップのために、メンターとなる人を見つけたい。
共有したい情報があるのに手段がないとき
- 個人的な体験や感情を多くの人に伝えたい場合:
- 旅行の感動や美味しい料理の写真を多くの友人やフォロワーにシェアしたい。
- 日々の出来事や考えを気軽に発信し、共感を得たい。
- 自分の作品や創作活動を広く発表し、フィードバックを得たい。
- 特定のグループ内で情報を効率的に共有したい場合:
- 部活動やサークルの連絡網を効率化し、全員に確実に情報を届けたい。
- 地域の自治会やボランティア団体で、イベントの告知や参加者募集を行いたい。
- 共同プロジェクトで、チームメンバーと資料や進捗状況をリアルタイムで共有したい。
日常生活における「モノ」との連携を求めるとき
- 離れた場所にあるモノを操作したい場合:
- 外出先から自宅のエアコンをつけたり、照明を消したりしたい。
- ペットの様子を外出先から確認したり、餌をあげたりしたい。
- 鍵の閉め忘れがないか、遠隔で確認したい。
- 複数のモノが連携することで利便性を高めたい場合:
- スマートスピーカーに話しかけるだけで、テレビをつけたり、音楽を再生したりしたい。
- スマートフォンで開錠できるスマートロックと宅配ボックスを連携させ、荷物の受け取りを効率化したい。
- フィットネスバンドで計測した運動データを、健康管理アプリと連携させて一元的に管理したい。
防犯や見守り、安全・安心を確保したいとき
- 留守中の自宅や店舗の状況を知りたい場合:
- 外出中に防犯カメラの映像をスマートフォンで確認したい。
- 不審な動きがあった場合に、通知を受け取りたい。
- 高齢者や子どもの安全を見守りたい場合:
- 離れて暮らす親が、元気でいるか定期的に確認したい。
- 子どもが安全に帰宅したか、GPSで位置情報を確認したい。
- 体調が悪そうな親の異変を、いち早く察知して連絡を取りたい。
第4章:「つなぐ」ニーズを満たす成功事例
「つなぐ(Connects)」ニーズを満たす製品やサービスは、個人顧客が抱える孤独感や情報共有の課題を解消し、精神的な充足や新たな体験を提供することで、高い評価と支持を得ている。
ここでは、様々な業界における具体的な成功事例を挙げ、その「つなぐ」仕組みと、個人顧客に提供する価値を深掘りする。
事例1:SNSプラットフォーム(Instagram, Xなど)
つなぐ仕組み
InstagramやX(旧Twitter)といったSNSは、ユーザーが写真や動画、テキストを投稿し、それをフォロワーや不特定多数のユーザーと共有することで、物理的な距離を超えたコミュニケーションを可能にする。
コメント、いいね、ダイレクトメッセージ機能を通じて、リアルタイムでの交流を促進し、共通の興味関心を持つ人々が繋がりやすい環境を提供している。
顧客への価値
友人や家族との日々の出来事を手軽に共有し、関係性を維持できる。
共通の趣味や関心を持つ人々と繋がり、情報交換や共感を得られることで、孤独感が解消され、所属欲求が満たされる。
自分の投稿を通じて承認欲求が満たされ、社会との接点を実感できる。
事例2:オンラインゲーム(あつまれ どうぶつの森、Fortniteなど)
つなぐ仕組み
「あつまれ どうぶつの森」や「Fortnite」のようなオンラインゲームは、インターネットを通じて複数のプレイヤーが同時に同じ仮想空間で活動することを可能にする。
協力プレイや対戦、チャット機能などを通じて、現実世界では会えない友人や見知らぬ人とも共同作業やコミュニケーションを楽しめる。
顧客への価値
ゲームという共通の体験を通じて、リアルな友人との絆を深めたり、新しい友人を作ったりできる。
現実世界での人間関係に縛られず、共通の趣味を持つ仲間と気軽に交流できる場が得られる。
ストレスの解消だけでなく、共同作業による達成感や連帯感を味わえる。
事例3:マッチングアプリ(Pairs, Tinderなど)
つなぐ仕組み
PairsやTinderなどのマッチングアプリは、プロフィール情報や共通の興味関心を基に、恋愛や結婚を目的とした異性との出会いをサポートする。
地理的な制約や日常の出会いの機会の少なさを補完し、共通点のある相手と効率的にマッチングし、メッセージのやり取りを通じて関係性を発展させる機会を提供する。
顧客への価値
普段の生活では出会えない新しい異性と知り合う機会が増える。
自身のライフスタイルや価値観に合う相手を見つけやすく、効率的に関係を築くことができる。
真剣な出会いを求める人も、カジュアルな交流を求める人も、それぞれのニーズに合った相手と繋がれる。
事例4:オンラインコミュニティ(Discordサーバー、Redditコミュニティなど)
つなぐ仕組み
DiscordやRedditなどのオンラインコミュニティプラットフォームは、特定のテーマや関心事に基づいてユーザーが集まり、テキストチャット、音声通話、情報共有を行う場を提供する。
匿名性や気軽さがあり、深い専門知識の共有からカジュアルな雑談まで、多様な交流が可能である。
顧客への価値
ニッチな趣味や専門分野について語り合える仲間を見つけられる。
同じ悩みや課題を抱える人々と共感し、情報や解決策を共有できる。
リアルな人間関係に疲れた時でも、気兼ねなく参加できる居場所があると感じられる。
事例5:遠隔地とつながるデバイス(スマートスピーカー、見守りカメラなど)
つなぐ仕組み
スマートスピーカー(例:Amazon Echo Show)は、音声通話やビデオ通話機能を備え、離れた家族と手軽に会話できる。
見守りカメラは、外出先から自宅の様子をリアルタイムで確認したり、センサーで異常を検知して通知を送ったりすることで、安心を提供する。
顧客への価値
離れて暮らす高齢の親や子どもとのコミュニケーションが容易になり、顔を見て話せることで安心感が得られる。
外出中も自宅の状況を把握でき、防犯やペットの見守りを通じて、心配事を軽減できる。
いざという時の安否確認や、すぐに駆けつけられない状況での心の支えとなる。
これらの事例は、「つなぐ」という個人顧客のニーズが、多様な形で実現され、具体的な精神的な充足や新たな体験を提供していることを示している。
単に機能を提供するだけでなく、個人顧客がどのように孤立や断絶を解消し、より豊かで充実した社会生活を送れるのかを明確に提示することが、製品やサービスの成功には不可欠である。
次の章では、これまでの考察を踏まえ、「つなぐ」がいかに人と人、人とモノの距離を縮め、新たな体験と豊かさをもたらすかについて総括する。
第5章:総括——「つなぐ」は、人やモノとの距離を縮め、新たな体験と豊かさをもたらす
これまでの議論を通じて、「つなぐ(Connects)」というニーズが、単に物理的な距離を縮めることにとどまらない、個人顧客の根源的な欲求であることが明らかになっただろう。
個人は、物理的な距離や心の隔たり、情報の分断がもたらす孤独感や不便さから解放され、その分を自分にとって本質的な価値、例えば深い人間関係の構築、共感の獲得、新たな発見、そして安心感といった「本当に求めていること」に意識とエネルギーを向けたいと願っているのだ。
マーケターは、この「つなぐ」ニーズを深く理解し、自社の商品やサービスが個人顧客のどのような潜在的な孤立や情報共有の課題を解決できるのか、そしてその結果としてどのような「心の距離の解消」や「新たな体験の創造」、「生活の質の向上への足がかり」を提供できるのかを明確にすることが重要である。
たとえば、
- 個人顧客が遠く離れた家族や友人とコミュニケーションを取りたい状況で、どうすれば手軽で心温まる交流を提供できるか?
- 個人顧客が共通の趣味や関心を持つ仲間を見つけたいと感じる中で、どうすれば安全で活発なコミュニティを提示できるか?
- 個人顧客が日常生活の中で、モノ同士が連携しないことで不便を感じるときに、どうすればシームレスな自動化や安心感を提供できるか?
といった問いを常に持ち続ける必要がある。
「つなぐ」は、単なる機能的価値ではなく、個人の孤独感の軽減や、社会的な充足感の向上に直結する感情的価値も内包している。
提供する製品やサービスが、個人顧客にとって「分断された世界を繋ぎ合わせ、より豊かな人間関係や可能性を引き出すパートナー」となるとき、それは単なる消費財を超え、顧客の心に深く響く存在となるだろう。

