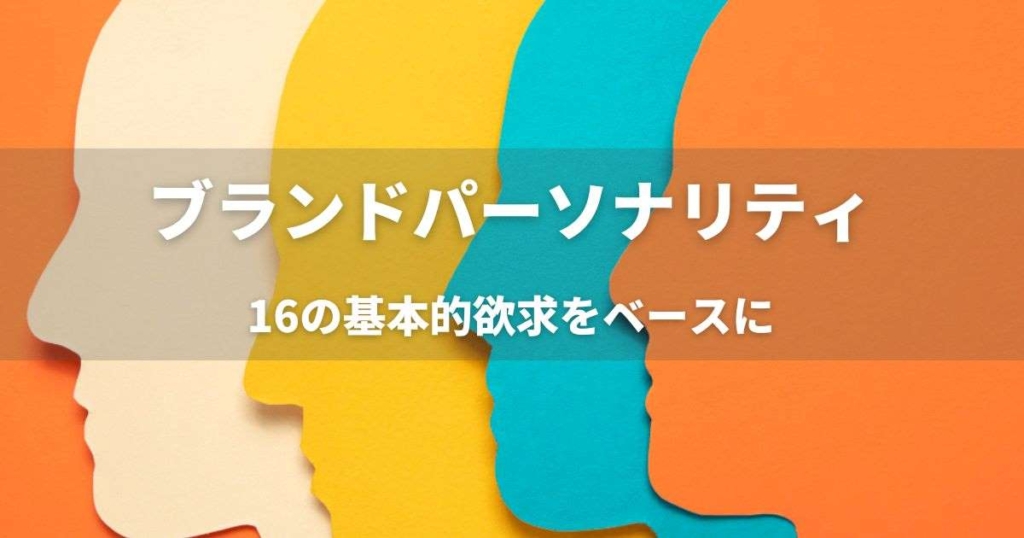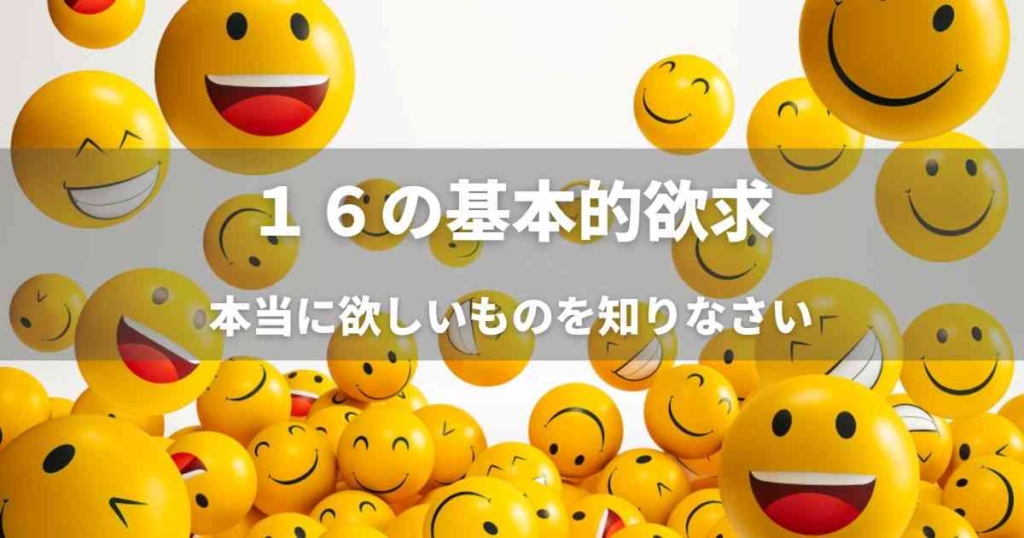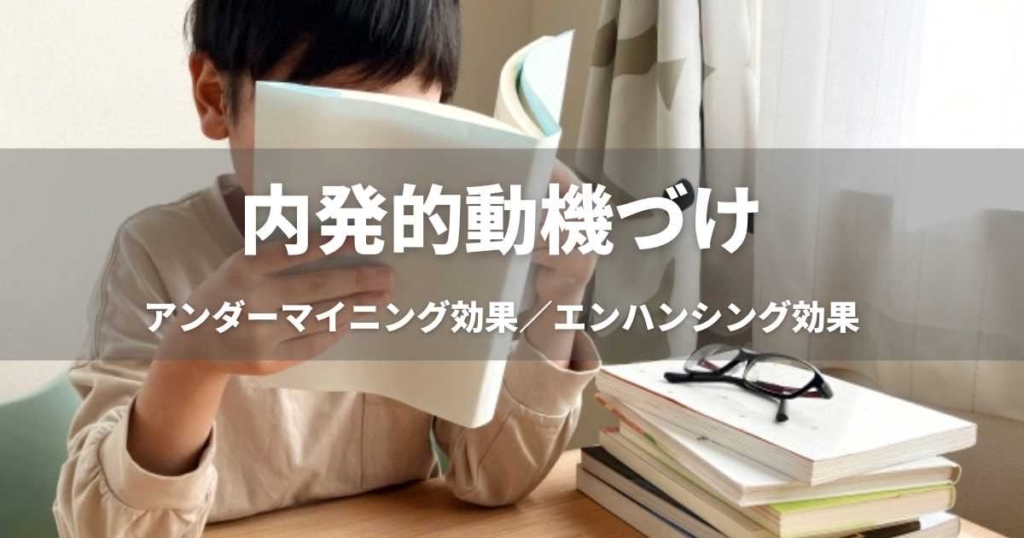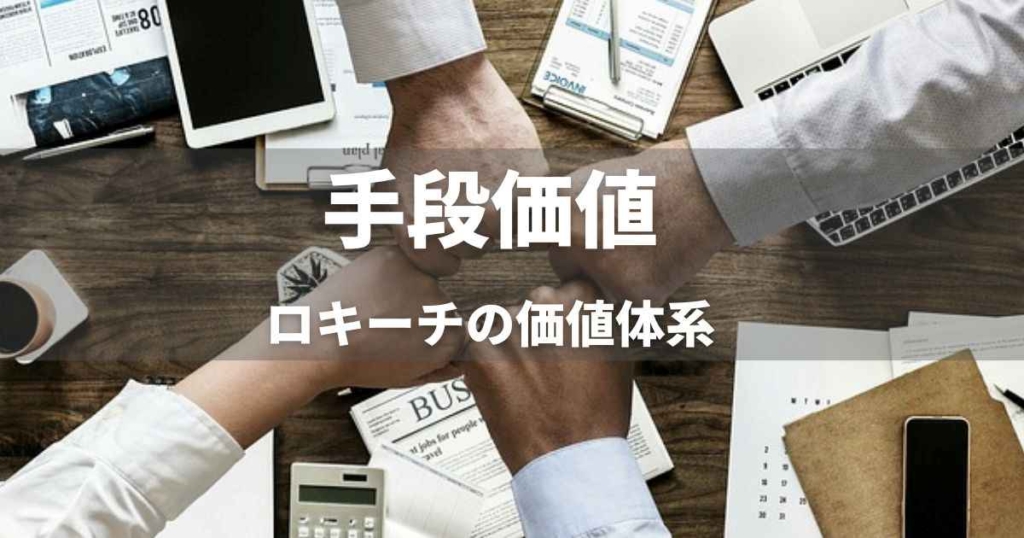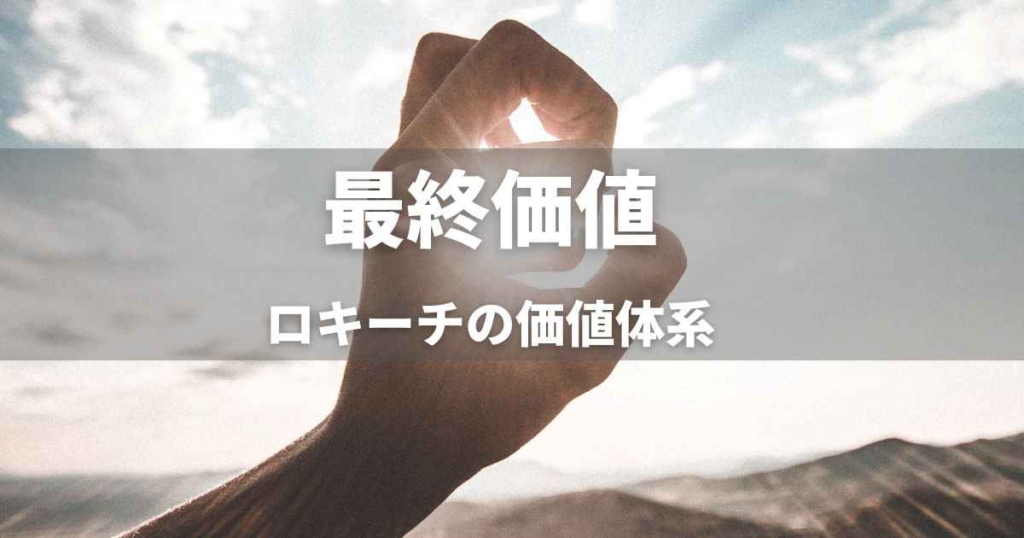心理法則– category –
-

ブランドパーソナリティの作り方 欲求フレームの活用
ブランディングに極めて重要な役割を果たすとされるブランドパーソナリティ。 消費者がブランドから連想される人となりのようなものを意味する。 今回の記事では、このブランドパーソナリティが消費者の頭の中に自然発生するのをただ待つのではなく、マー... -

16の基本的欲求 マーケティングに使えるアナザー・マズロー
人は誰もが、一つひとつに程度の差はあれ、16の基本的欲求を持つという。 力(power)、独立(independence)、好奇心(curiosity)、承認(acceptance)、秩序(order)、貯蔵(saving)、誇り(honor)、理想(idealism)、交流(social contact)、家族... -

内集団バイアス vs. 黒い羊効果 いじめと身びいきの密なる関係
「内集団バイアス」とは、自分が所属する集団、すなわち「内集団」のメンバーをより好意的に評価してしまう心理傾向をいう。 「内集団びいき」とも言われる。 この心理作用を念頭に、マーケターがオンラインやオフラインを問わず、ブランドのファンたちが... -

マクレランドの欲求理論とは? 人間を動機づける3つの欲求
「欲求理論」とは人の行動を動機づけるもととなる社会的欲求を言い当てたもの。 「達成欲求(動機)」「権力欲求(動機)」「親和欲求(動機)」の3つがあるという。 もともと働く人を研究対象に生まれた理論だが、たった3つの欲求で人の行動を説明する枠... -

内発的動機づけを高める方法とは? カギは努力の娯楽化と有能感
内発的動機づけとは、何ら報酬や罰が与えられるわけでもないのに、内面から湧き起こる欲求に駆り立てられ、行動が動機づけられることをいう。 その内面の欲求には、自らの選択で主体的に行動したいという「自律性」、能力を発揮したい、役に立っていたいと... -

接近と回避のモチベーション(動機づけ):消費者行動の根っこに迫る
「快」に接近し、「不快」を回避する。人は常にそう動機づけられている。 その根底にはフロイトが提唱した「快楽原則」があるという。 その原則によれば、人には無意識的に快楽を追求するという精神構造を生まれつき備えていて、実は消費者行動もその影響... -

「動因」と「誘因」のモチベーション:購買行動を促す2大要因
消費者からいかに購買行動を引き出すか? つきつめるところ、多くのマーケターにとっては最大の関心事はそこだろう。 その購買行動が引き出されるメカニズムの最もシンプルな説明が「動因」と「誘因」だ。 「動因」とは人の内面に生じる「欲しい」という... -

シュワルツの価値理論: ポジショニング戦略の道しるべ
「シュワルツの価値理論」―普遍的な価値を10タイプに 以前の記事で「ロキーチの価値体系」を前編・後編にわけて紹介した。 人が望ましいと考える「価値(value)」の分類体系の一つで、「最終価値」と「手段価値」に二分されるのが特徴だ。 2つの価値のも... -

「手段価値」とは何か? ロキーチの価値体系 ≪後編≫
誰にとっても望ましいとされる普遍的な価値の体系、「ロキーチの価値体系」。 「最終価値」と「手段価値」に分かれるが、後編にあたる本記事では「手段価値」を取り上げる。 「最終価値」が望ましいとされる究極の状態なら、「手段価値」は、その「最終価... -

「最終価値」とは何か? ロキーチの価値体系 ≪前編≫
誰もが望ましいと感じる普遍的な価値の分類体系に「ロキーチの価値体系」がある。 「最終価値」と「手段価値」に分かれ、それぞれ18の下位価値があり、合計で36の価値がリスト化されている。 抽象度が高く、一つひとつの価値の深遠な意味までは理解が及ば...