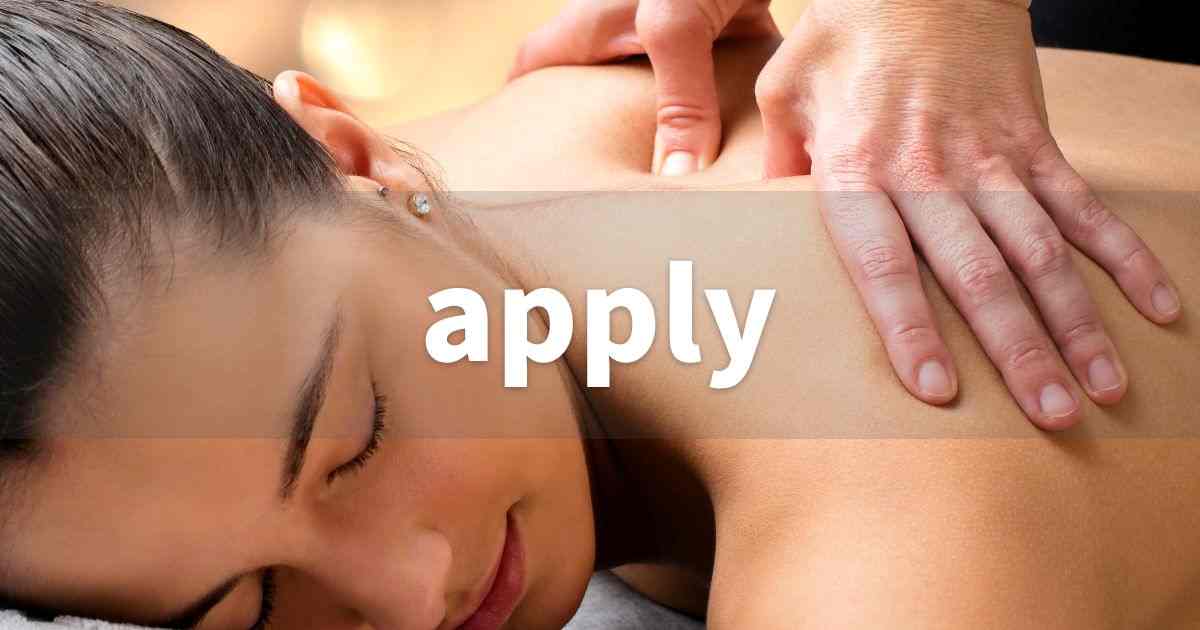「apply」という英単語、意味は知っているのに、文脈によって迷う——そんな経験はないだろうか。
「塗る」「申し込む」「適用する」「注ぐ」「加える」など、訳語は多岐にわたり、場面によって意味が大きく変化する。
その多義性ゆえに、使い分けが直感的に捉えづらく、添える対象や目的との関係性によってニュアンスの取り違えが起こりやすい。
ときに軟膏を塗り、ときに職に応募し、ときに理論を適用し、ときに圧力を加え、ときに努力を注ぎ込む—— 「apply」は、物理・制度・抽象・心理・技術の領域をまたいで機能する、極めて柔軟かつ目的志向的な動詞である。
本稿では、「対象に必要なものを重ねることで、効果や効力を発揮させる」というコアイメージを出発点に、「apply」が持つ意味の広がりと類義語との違いを体系的に整理する。
0.イントロダクション:「apply」の多義性とコアイメージの提示
【意味】
- (物理的に)塗る、貼る、当てる
- (規則・理論などを)適用する
- (職・許可などを)申し込む、志願する
- (注意・努力などを)注ぐ、向ける
- (力・圧力などを)加える
「apply」は、日常生活からビジネス、学術、制度、心理、物理現象に至るまで、幅広い文脈で登場する基本動詞である。
「塗る」「適用する」「申し込む」「注ぐ」「加える」など、日本語訳は多岐にわたり、場面によって意味が大きく変化する。
身体動作・制度的手続き・抽象的思考・物理的作用など、具体と抽象、個人と制度をまたぐため、直感的な理解が難しく、使い分けに迷うことも少なくない。
たとえば:
- apply sunscreen to your skin(肌に日焼け止めを塗る)
- apply for a job(仕事に応募する)
- apply a rule to a case(ある事例に規則を適用する)
- apply pressure to the wound(傷口に圧力を加える)
- apply oneself to study(勉強に専念する)
これらは一見すると無関係に見えるが、いずれも「ある対象に、必要なものを重ねることで、効果や機能を発揮させる」という共通の構造を持っている。
つまり、「apply」の多義的な用法はすべて、“目的達成のために、何かを対象に重ねるというコアイメージに根ざしている。


このイメージを押さえることで、「apply」が持つ意味の広がりを、辞書的な暗記ではなく、動作のリアリティとして直感的に理解することが可能となる。
次章では、このコアイメージについて詳しく解説する。
1.語源とコアイメージ:「必要なものを、対象に重ねる」動作
「必要なものを、対象に重ねることで、効果・効力・機能を発揮させる」=「施す」「適用する」「注ぐ」

語源は中英語 applien に由来し、古フランス語 appliquer(添える、密着させる)を経て、ラテン語 applicare(〜に向けて添える、接触させる)に遡る。
この applicare は ad-(〜に向かって)+ plicare(折る、重ねる)から成り、もともとは「何かを他のものに折り重ねる・密着させる」という物理的な動作を表していた。
つまり、「apply」は本来、ある対象に対して、必要なものを重ねることで、効果や機能を発揮させるという動作を表す語だった。
たとえば潤滑油のように、直接的な力ではなく、対象に“重ねる”ことで機能を滑らかに発揮させるもの——それが apply の本質である。

物理的な塗布も、制度への申し込みも、理論の適用も、すべては「目的に応じて働きを及ぼすために、何かを重ねる」行為なのだ。
実は、私たちが日常的に使っている「アプリ(application)」という言葉も、この apply に由来している。
スマートフォンのアプリは、ユーザーの目的に応じて機能を“重ねる”ことで、操作や情報処理を可能にする道具であり、まさに apply のコアイメージを体現していると言える。
この「重ねる」感覚は、現代英語においても抽象化されながら保持されており、「塗る」「申し込む」「適用する」「注ぐ」「加える」など、さまざまな文脈で機能している。
たとえば:
- apply sunscreen to your skin(肌に日焼け止めを塗る)=物理的に物質を肌に添える
- apply for a job(仕事に応募する)=制度に対して自分の情報を添える
- apply a rule to a case(ある事例に規則を適用する)=抽象的な枠組みを事例に重ねる
- apply pressure to the wound(傷口に圧力を加える)=力を対象に密着させる
- apply oneself to study(勉強に専念する)=注意・努力を対象に向けて注ぎ込む
これらは一見バラバラに見えるが、いずれも「主体が、目的達成のために、何かを対象に重ねる」ことで、効果や関係性が生じるという共通の構造を持っている。
なお、「apply」は動詞として使われるだけでなく、名詞形(application)や形容詞形(applicable)としても用いられ、コアイメージは品詞を越えて保持される。
たとえば:
- job application(職への応募)=制度に対して情報を添える行為
- applicable rules(適用可能な規則)=ある対象に重ねることができる枠組み
いずれも「対象に向けて、必要なものを重ねる」というコアイメージに根ざしており、品詞が変わってもその多義性は健在である。
日本語では「塗る」「申し込む」「適用する」「注ぐ」「加える」などと訳されるが、英語の「apply」はそれらを一つの「対象に向けて、必要なものを重ねる」という感覚で統合している。


この「重ねる」感覚を押さえることで、「apply」が持つ多義的な意味の広がりを、辞書的な暗記ではなく、動作のリアリティとして直感的に理解することが可能となる。
次章では、このコアイメージをもとに、文脈ごとの具体的な用法を整理していく。
2.コアイメージの展開:文脈別に見る「重ねる」の多様性
前章では、「apply」の語源とコアイメージ——“必要なものを、対象に重ねる”という動作——について確認した。
ここではそのイメージが、現代英語においてどのように文脈ごとに姿を変え、意味の広がりを見せているかを整理していく。
「apply」は、単なる「塗る」や「申し込む」にとどまらず、場面に応じて「適用する」「注ぐ」「加える」「専念する」など、さまざまな役割を担う動詞である。
| 用法カテゴリ | 例文 | コアイメージとのつながり |
|---|---|---|
| 物理的に塗る・貼る | apply lotion to the skin | 物質を対象に添えて効果を発揮させる |
| 制度・職に申し込む | apply for a visa | 自分の情報を制度に添えることで審査を受ける |
| 規則・理論を適用する | apply the rule to this case | 抽象的な枠組みを事例に重ねる |
| 圧力・力を加える | apply pressure to the wound | 物理的な力を対象に密着させる |
| 注意・努力を注ぐ | apply oneself to study | 精神的資源を対象に向けて注ぎ込む |
日常文脈での「apply」使用例
① 物理的に塗る・貼る
- She applied sunscreen before going outside.
- 彼女は外出前に日焼け止めを塗った。
- =物質を肌に添えて、保護効果を発揮させる。
- 彼女は外出前に日焼け止めを塗った。
② 注意・努力を注ぐ
- He applied himself to learning Japanese.
- 彼は日本語学習に専念した。
- =精神的な力を対象に向けて注ぎ込む。
- 彼は日本語学習に専念した。
③ 道具・技術を使う
- You can apply this method to other problems.
- この方法は他の問題にも応用できる。
- =技術を対象に重ねて機能させる。
- この方法は他の問題にも応用できる。
制度・ビジネス文脈での「apply」使用例
① 職・許可に申し込む
- She applied for a position at the company.
- 彼女はその会社の職に応募した。
- =自分の情報を制度に添えて審査を受ける。
- 彼女はその会社の職に応募した。
② 規則・理論を適用する
- The policy was applied to all departments.
- その方針はすべての部署に適用された。
- =抽象的な枠組みを組織に重ねる。
- その方針はすべての部署に適用された。
③ 技術・知識を応用する
- We applied our research to real-world problems.
- 私たちは研究成果を現実の課題に応用した。
- =知識を対象に重ねて機能させる。
- 私たちは研究成果を現実の課題に応用した。
物理・技術文脈での「apply」使用例
① 圧力・力を加える
- Apply firm pressure to stop the bleeding.
- 出血を止めるためにしっかり圧力を加えてください。
- =力を対象に密着させて効果を発揮させる。
- 出血を止めるためにしっかり圧力を加えてください。
② 材料・処理を施す
- The technician applied a protective coating.
- 技術者は保護コーティングを施した。
- =物質を対象に添えて機能を加える。
- 技術者は保護コーティングを施した。
③ 操作・制御を加える
- Apply the brakes gently.
- ブレーキは優しくかけてください。
- =力を対象に添えて制御する。
- ブレーキは優しくかけてください。
抽象・心理文脈での「apply」使用例
① 専念する・集中する
- He applied his full attention to the task.
- 彼はその作業に全神経を集中させた。
- =注意力を対象に向けて添える。
- 彼はその作業に全神経を集中させた。
② 応用する・転用する
- Can we apply this idea to marketing?
- このアイデアをマーケティングに応用できるだろうか?
- =概念を別の対象に重ねて機能させる。
- このアイデアをマーケティングに応用できるだろうか?
③ 適用可能である
- The rule doesn’t apply here.
- この規則はここでは適用されない。
- =枠組みが対象に重ねられない状況。
- この規則はここでは適用されない。
このように、「apply」は物理的な塗布から制度的な申し込み、抽象的な適用、心理的な集中まで、多様な領域で「対象に必要なものを重ねる」動作として機能している。
訳語としては「塗る」「申し込む」「適用する」「注ぐ」「加える」などが挙げられるが、英語の「apply」はそれらを一つの「目的達成のために、対象に必要なものを重ねる」という感覚でつなぎ直すことができる。
この視点を持つことで、「apply」の多義性を文脈に応じて自然に使い分ける力が養われるだろう。
次章では、こうした意味の広がりを踏まえたうえで、「use」「put」「submit」「implement」「enforce」などの類義語との違いを明確にしていく。
3.実践的な理解:類義語とのコアイメージ比較
「apply」は「塗る」「申し込む」「適用する」「注ぐ」「加える」などと訳されることが多いが、英作文や語彙選びの場面では、似たような文脈で「use」「put」「submit」「implement」「enforce」などの語が思い浮かぶこともあるだろう。
いずれも「何かを対象に働きかける」「機能や効果を発揮させる」行為に関わる語であり、文脈によっては「apply」と意味が重なるように見えるが、重ねる対象の性質、主語の立場、行為の抽象度や強制性において違いがある。
以下の表は、それぞれのコアイメージと違いのポイントを整理したものである。
| 単語 | コアイメージ | 違いのポイント |
|---|---|---|
| use | 手元のものを目的に応じて使う | 選択・活用の自由度が高く、添える動作は伴わない |
| put | 物理的に何かを置く・載せる | 動作は具体的だが、目的性や効果は限定的 |
| submit | 制度や権威に対して正式に提出する | 形式性・義務性が強く、添える対象は情報や書類 |
| implement | 計画や方針を現実に実行する | 抽象的な内容を現場に落とし込む実行性に焦点 |
| enforce | 規則や力を強制的に適用する | 強制力を伴う適用。受け手の選択余地がない |
| apply | 必要なものを対象に重ねる | 効果・効力を発揮させるための柔軟な動作 |
ここから、文脈ごとの違いを英文と和訳のセットで紹介する。ニュアンスの違いを直感的に理解してほしい。
① apply vs use:目的への働きかけの形式性と添え方の違い
- I used this tool to fix the problem.
- この道具を使って問題を解決した。
- =手元のものを選んで活用する。添える動作は伴わない。
- この道具を使って問題を解決した。
- I applied this tool to the damaged area.
- この道具を損傷部分に当てて使った。
- =対象に添えて効果を発揮させる。
- この道具を損傷部分に当てて使った。
▶︎「use」は活用、「apply」は添える——対象との接触と目的性の違い。
② apply vs put:物理的動作と目的性の違い
- He put the book on the shelf.
- 彼は本を棚に置いた。
- =物理的な配置。目的や効果は限定的。
- 彼は本を棚に置いた。
- He applied glue to the edge of the paper.
- 彼は紙の端に接着剤を塗った。
- =対象に添えて機能を発揮させる。
- 彼は紙の端に接着剤を塗った。
▶︎「put」は配置、「apply」は施す——動作の目的と効果の違い。
③ apply vs submit:制度的手続きにおける形式性の違い
- She submitted her resume to the company.
- 彼女は会社に履歴書を提出した。
- =制度に対して正式な情報を差し出す。
- 彼女は会社に履歴書を提出した。
- She applied for the position last week.
- 彼女は先週その職に応募した。
- =制度に対して自分を添えることで審査を受ける。
- 彼女は先週その職に応募した。
▶︎「submit」は提出、「apply」は志願——形式性と主体性の違い。
④ apply vs implement:抽象的な適用と現実的な実行の違い
- The company implemented a new policy.
- その会社は新しい方針を実行に移した。
- =抽象的な計画を現場に落とし込む。
- They applied the policy to all departments.
- 彼らはその方針をすべての部署に適用した。
- =枠組みを対象に添えて機能させる。
- 彼らはその方針をすべての部署に適用した。
▶︎「implement」は実行、「apply」は適用——抽象度と動作の焦点が異なる。
⑤ apply vs enforce:規則・力の「適用」の強制性の違い
- The school enforced strict rules on attendance.
- その学校は出席に関する厳しい規則を強制した。
- =強制力を伴う適用。受け手の選択余地がない。
- その学校は出席に関する厳しい規則を強制した。
- The rule was applied to all students.
- その規則はすべての生徒に適用された。
- =枠組みを添えて機能させる。強制性は文脈次第。
- その規則はすべての生徒に適用された。
▶︎「enforce」は強制、「apply」は適用——力の有無と受け手の自由度が異なる。
このように、同じ「使う」「置く」「提出する」「実行する」「適用する」と訳される語でも、英語では「活用」「配置」「手続き」「実行」「強制」など、添える行為の性質や関係の深さに細かなニュアンスの違いが存在する。
「apply」はその中でも、主体が目的達成のために、必要なものを対象に重ねることで、効果・効力・機能・関係性を柔軟に表現できる動詞である。
次章では、こうした違いを踏まえたうえで、実践的な使い方を確認していく。
4.アウトプット演習:空欄補充でニュアンスを体得する
以下の文の空欄に、適切な語句(apply / use / put / submit / implement / enforce)を入れてみよう。
文脈に応じたニュアンスの違いを意識することで、単語の選択精度が高まる。
- The company _ the new policy last month.
- (その会社は先月新しい方針を実行に移した)
- 答え:implemented ※抽象的な計画を現場に落とし込む。
- He _ the book on the table and left.
- (彼は本をテーブルに置いて立ち去った)
- 答え:put ※物理的に配置する。目的性は限定的。
- She _ her application before the deadline.
- (彼女は締切前に申請書を提出した)
- 答え:submitted ※制度に対して正式な情報を差し出す。
- The nurse _ ointment to the wound carefully.
- (看護師は傷口に注意深く軟膏を塗った)
- 答え:applied ※対象に添えて効果を発揮させる物理的な動作。
- The school _ strict rules on smartphone use.
- (その学校はスマートフォン使用に厳しい規則を適用した)
- 答え:enforced ※強制力を伴う適用。受け手の選択余地がない。
- We _ this software to manage inventory.
- (私たちはこのソフトウェアを在庫管理に使っている)
- 答え:use ※目的に応じて手元の道具を活用する。
このように、同じ「使う」「置く」「提出する」「実行する」「適用する」と訳される行為であっても、文脈によって選ぶべき単語は異なる。
- apply:対象に必要なものを添える・重ねる。効果・効力・機能を発揮させる柔軟な動詞
- use:目的に応じて手元のものを活用する。添える動作は伴わない
- put:物理的に配置する。目的性や効果は限定的
- submit:制度や権威に対して正式に提出する。形式性・義務性が強い
- implement:抽象的な計画や方針を現実に実行する。実行性に焦点
- enforce:規則や力を強制的に適用する。受け手の自由度がない
それぞれのコアイメージを把握することで、場面に応じた語の選択がより的確に行えるようになる。
ここまでの整理を踏まえ、最後に「apply」の意味を簡潔にまとめておこう。
5.まとめ:コアイメージで「apply」の多義性を統合する
「apply」は、軟膏の塗布から制度への申し込み、理論の適用、圧力の加加、努力の注入まで、幅広い場面で使われる基本動詞である。
その多義性は、「対象に必要なものを重ねる」というコアイメージに根ざしており、文脈に応じて「施す」「申し込む」「適用する」「注ぐ」「加える」などの意味を担う。
このイメージを軸にすれば、訳語の違いに惑わされず、場面ごとの使い分けも自然にできるようになる。
語義の暗記ではなく、動作の構造——「何かを対象に重ねることで、機能や効果を発揮させる」——をイメージすることが、語感を伴った理解への近道となる。