「leave」という英単語、意味は知っているのに、文脈によって迷う——そんな経験はないだろうか。
「去る」「残す」「任せる」「辞める」など、訳語は多岐にわたり、場面によって意味が大きく変化する。
その多義性ゆえに、使い分けが直感的に捉えづらく、誤解やニュアンスの取り違えが起こりやすい。
ときに空間を離れ、ときに物を残し、ときに責任を委ねる——「leave」は、物理・心理・制度の領域をまたいで機能する、極めて柔軟かつ繊細な動詞である。
本稿では、「何かを後に残して去る」という原義に由来する“残して去る”というコアイメージを出発点に、「leave」が持つ意味の広がりと類義語との違いを体系的に整理する。
0.今回のテーマは「leave」
【意味】
- (場所・人・物を)去る、離れる
- (物・人・状況を)残す、置いていく
- (任務・判断などを)委ねる、任せる
- (状態・結果などを)そのままにしておく
- (仕事・学校などを)辞める、退職する
「leave」は、日常会話からビジネス、法律、感情表現まで、極めて広範な文脈で登場する基本動詞である。
「去る」「残す」「任せる」「辞める」など、日本語訳は多岐にわたり、文脈によって意味が大きく変化する。

しかもそれらの意味は、方向性が逆であるかのように見える——「去る」と「残す」は、動作のベクトルが正反対だからだ。
しかし、英語の「leave」が持つ意味の広がりは、単なる対義語の混在ではなく、「残して去る」という一貫したコアイメージに根ざしている。
たとえば:
- leave the room(部屋を去る)
- leave your bag here(カバンをここに置いていく)
- leave it to me(それは私に任せて)
- leave the door open(ドアを開けたままにしておく)
- leave the company(会社を辞める)
これらは一見バラバラに見えるが、いずれも「(場所や状態を)残して去る」ことで、空間的・心理的・制度的な変化を生じさせるという共通の構造を持っている。
本稿では、「leave」の中心にある“何かを残して去る”という原義を起点に、意味の広がりと類義語との違いを体系的に整理する。
辞書的な意味の暗記ではなく、英語の“状況感覚”として「leave」を理解することを目指す。
1.なぜ「leave」は難しい?多義性の3つの理由
「leave」が難解に感じられる理由は、主に以下の3点に集約される。
① 意味の幅が広く、文脈によって訳語が大きく変化する
たとえば以下のような用例がある:
- leave the room(部屋を去る)
- leave your bag here(カバンをここに置いていく)
- leave it to me(それは私に任せて)
- leave the door open(ドアを開けたままにしておく)
- leave the company(会社を辞める)
- leave someone alone(誰かをそっとしておく)
これらは一見すると無関係に見えるが、いずれも「(場所や状態を)残して去る」ことで、空間的・心理的・制度的な変化を生じさせるという共通の構造を持っている。
つまり、「leave」は物理的な移動から心理的な距離、制度的な離脱まで、幅広い意味領域をカバーしており、文脈によって訳語が大きく変化する。
なお、日本語では「去る」「残す」「任せる」「辞める」など、訳語が多岐にわたるが、それぞれの意味が逆方向に見えるため、理解が混乱しやすい。
② 空間・心理・制度的な意味が混在している
「leave」は、日常会話からビジネス、法律、感情表現まで、非常に多様な分野で使われる。
- 空間的には「その場を離れる」
- 心理的には「干渉しない」「任せる」
- 制度的には「退職する」「権限を委ねる」
このように、具体的な動作から抽象的な判断、制度的な手続きまで、意味のスケールが極端に広いため、単語の印象が定まらず、使い分けが難しくなる。
たとえば:
- leave the meeting early(会議を早退する)=空間的離脱
- leave the decision to her(判断を彼女に任せる)=心理的委任
- leave the company(会社を辞める)=制度的離脱
いずれも「leave」だが、意味の領域がまったく異なる。
③ 類義語との違いが直感的に捉えづらい
「abandon」「quit」「let」「remain」「stay」など、似たような文脈で使われる単語との違いが明確でないため、誤用が起こりやすい。
たとえば:
- abandon:意図的に見捨てるニュアンスが強く、責任放棄を含む
- quit:制度的に辞めることに焦点があり、継続性の断絶を示す
- let:許容・容認の意味が中心で、能動的な手放しとは異なる
- remain:主語が「残る」ことに焦点があり、「leave」とは視点が逆
- stay:その場にとどまることを意味し、「leave」とは動作の有無が対照的
このように、「leave」は意味の広がりが大きく、文脈によってニュアンスが激しく変化するため、辞書的な理解だけでは不十分である。
次章では、「leave」のコアイメージ——“残して去る”=「去る・残す・委ねる」——について詳しく解説する。
2.コアイメージは「“後に残して去る”感覚」。語源から読み解く
「何かをその場に“残して”、自分はそこから“去る”」=「置いていく」「残して離れる」「委ねて離れる」
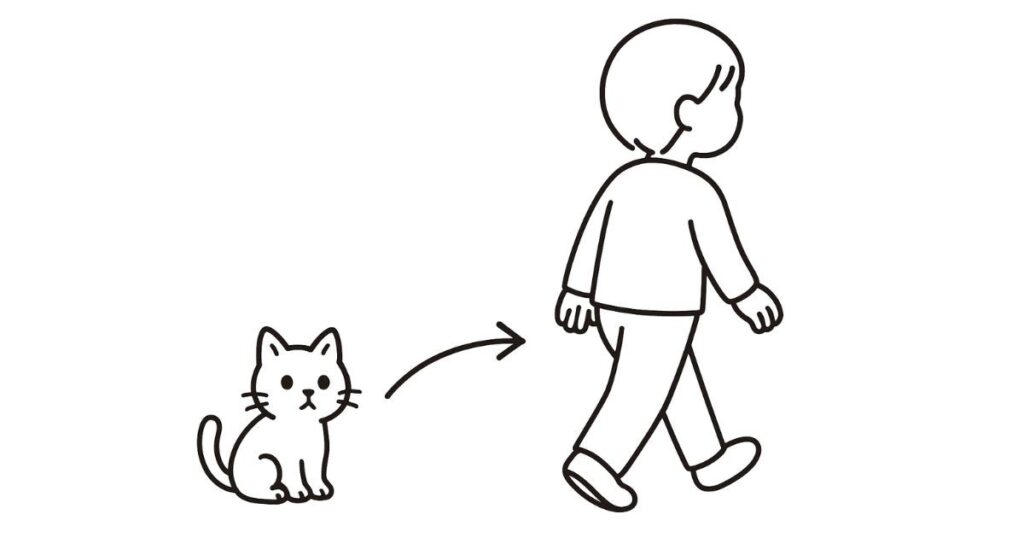
語源は古英語 lǣfan(残す、許す)に由来し、さらにゲルマン祖語 laibijan(残す)へと遡る。
この語根は「laibō(残り、遺産)」とも関連し、現代英語の「leave」は「何かを後に残して去る」という動作の二面性を核に、多義的な意味へと広がっている。
もともとは「物をその場に残す」「人を自由にする」といった物理的・心理的な動作を指していたが、現代英語ではこのイメージが抽象化され、「去る」「残す」「任せる」「辞める」「放置する」など、さまざまな文脈で機能する動詞となっている。

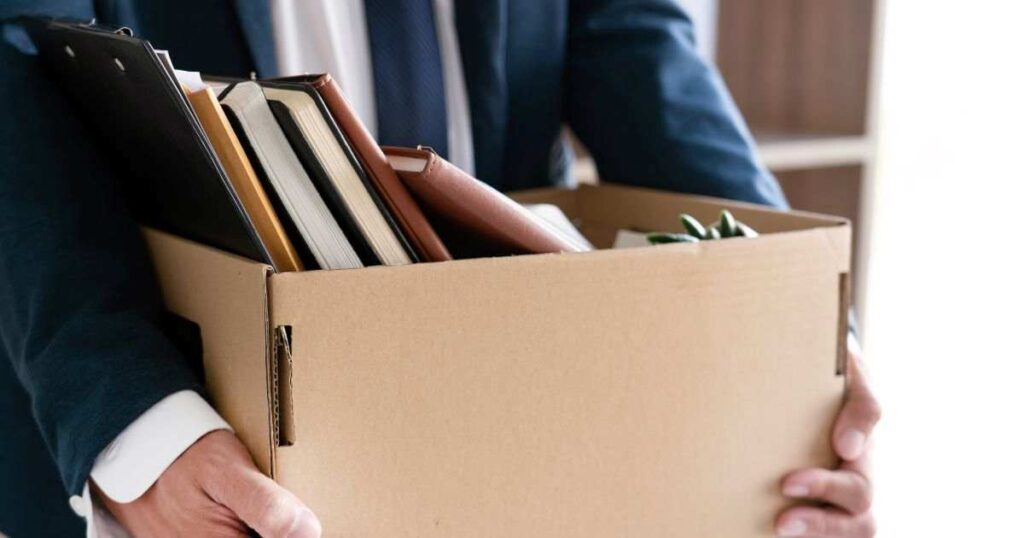
この「残して去る」感覚は、単なる移動や放置ではなく、対象との関係性を変化させることで、空間的な距離・心理的な自由・制度的な委任を生み出す。
つまり「leave」は、何かを“後に残す”ことで状況に変化を与える動詞なのだ。
たとえば:
- leave the room(部屋を去る)=自分の存在を空間から“離す”
- leave your bag here(カバンをここに置いていく)=物をその場に“残す”
- leave it to me(それは私に任せて)=判断や責任を“委ねる”
- leave the door open(ドアを開けたままにしておく)=状態を“そのままにする”
- leave the company(会社を辞める)=制度的な所属を“断つ”
これらは一見バラバラに見えるが、いずれも「何かを残して自分は去る」という構造を持っており、空間・責任・制度・心理のいずれかに変化を生じさせる。
なお、「leave」は動詞だけでなく名詞としても使われる。
たとえば:
- on leave(休暇中)=職務から一時的に“離れている”状態
- maternity leave(産休)=制度的に“離脱”を許された期間
いずれも「残して去る/距離を置く」というコアイメージに根ざしており、名詞形でもその多義性は健在である。
日本語では「去る」「残す」「任せる」「辞める」など、文脈によって訳語が大きく変化するが、英語の「leave」はそれらを一つの「何かを後に残して去る」感覚で統合している。
この「残して去る」感覚を押さえることで、「leave」が持つ多義的な意味の広がりを、辞書的な暗記ではなく、状況のリアリティとして直感的に理解することが可能となる。
次章では、このコアイメージをもとに、文脈ごとの具体的な用法を整理していく。
3.コアイメージから広がる多義的な用法
「leave」が持つ「残して去る/距離を置く」という原義は、現代英語において「去る・残す・委ねる・放置する・辞める」といった多義的な意味へと進化している。
この「残して去る」感覚は、物理的な移動だけでなく、心理的な距離の確保や制度的な離脱、責任の委任など、文脈に応じて多様な意味を生み出している。
以下の表は、その代表的な用法を整理したものである。
| 用法カテゴリ | 例文 | コアイメージとのつながり |
|---|---|---|
| 空間的に去る | leave the room | 自分の存在をその場から“離して”後に残す |
| 物を残す | leave your bag here | 所有物を“残して”その場に置いていく |
| 判断・責任を委ねる | leave it to me | 意思決定を“委ねて”自分は離れる |
| 状態をそのままにする | leave the door open | 状態を“維持したまま”その場を離れる |
| 制度的に辞める | leave the company | 所属を“断ち切って”制度から離脱する |
| 干渉せず放っておく | leave someone alone | 関与を“控えて”心理的な距離を置く |
このように、「leave」は単なる「去る」や「残す」ではなく、「何かをその場に残したまま離れる」ことで、空間・責任・制度・心理のいずれかに変化を生じさせる動詞として機能する。
以下では、日常・ビジネス・制度・心理文脈に分けて、具体的な使用例を確認していく。
日常文脈での「leave」使用例
① 空間的に去る
- I’ll leave now before it gets dark.
- 暗くなる前に出発するよ。
- =自分の存在をその場から“離して”、空間に変化を生じさせる。
- 暗くなる前に出発するよ。
② 物を残す
- You can leave your coat here.
- コートはここに置いておいていいよ。
- =所有物をその場に“残して”、自分はその場を離れる。
- コートはここに置いておいていいよ。
③ 状態をそのままにする
- Leave the window open while you’re airing the room.
- 部屋の換気中は窓を開けたままにしておいて。
- =状態を“維持したまま”その場を離れる。
- 部屋の換気中は窓を開けたままにしておいて。
ビジネス文脈での「leave」使用例
① 制度的に辞める
- She decided to leave the company last month.
- 彼女は先月会社を辞める決断をした。
- =制度的な所属を“離れて”、新たな方向へ移る行為。
- 彼女は先月会社を辞める決断をした。
② 判断・責任を委ねる
- Let’s leave the final decision to the client.
- 最終判断はクライアントに任せましょう。
- =意思決定を“委ねて”、自分は判断の場から退く。
- 最終判断はクライアントに任せましょう。
③ 一時的に離れる
- He is currently on leave for personal reasons.
- 彼は私的な理由で現在休職中です。
- =職務から一時的に“距離を置き”、責任を一時的に他者に委ねている状態。
- 彼は私的な理由で現在休職中です。
制度・心理文脈での「leave」使用例
① 干渉せず放っておく
- Just leave him alone for a while.
- しばらく彼をそっとしておいて。
- =関与を控え、“距離を置く”ことで心理的な余白を与える。
- しばらく彼をそっとしておいて。
② 遺言・遺産を残す
- He left everything to his daughter.
- 彼はすべてを娘に遺した。
- =所有物や意思を“託して”、自分はその管理から離れる。
- 彼はすべてを娘に遺した。
③ 結果を残す
- The accident left a deep scar in his memory.
- その事故は彼の記憶に深い傷を残した。
- =出来事が“去った後も”影響を残し続けている。
- その事故は彼の記憶に深い傷を残した。
このように、「leave」は物理的な移動だけでなく、心理的・制度的・社会的な“距離の確保”や“委任”“残存”を表す動詞である。
日本語では「去る」「残す」「任せる」「辞める」などと訳されるが、英語の「leave」はそれらを一つの「何かを残して去る」感覚で統合している。
この「残して去る」感覚を理解することで、「leave」が持つ多義的な意味の広がりを、文脈に応じて自然に使い分けることが可能となる。
次章では、こうした意味の広がりを踏まえたうえで、「abandon」「quit」「let」「remain」「stay」などの類義語との違いを明確にしていく。
4.類義語との違いを徹底比較
「leave」は「去る」「残す」「任せる」「辞める」などと訳されることが多いが、同じような文脈で使われる abandon、quit、let、remain、stay などとはニュアンスが異なる。
以下の表は、それぞれのコアイメージと違いを整理したものである。
| 単語 | コアイメージ | 違いのポイント |
|---|---|---|
| abandon | 見捨てる、放棄する | 意図的な放棄や責任放棄を含み、感情的・否定的ニュアンスが強い |
| quit | 制度的に辞める | 継続的な活動からの離脱に焦点。意志的で制度的な断絶を示す |
| let | 許す、許容する | 能動的に残して離れるのではなく、受動的に「許す」ニュアンスが中心 |
| remain | 残る | 主語が「残る」ことに焦点。「leave」は主語が「去る」視点 |
| stay | とどまる | 動作の有無と意志の違い。「leave」は動き、「stay」は静止 |
| leave | 残して去る | 空間・責任・制度・心理の境界を“残して離れる”ことで変化を生む |
ここから、類義語との違いを英文と和訳のセットで紹介する。文脈ごとのニュアンスの違いを直感的に理解してほしい。
① leave vs abandon:意図と責任の有無
- I abandoned the project halfway through.
- 途中でプロジェクトを放棄した。
- =責任を放棄した否定的なニュアンス。
- 途中でプロジェクトを放棄した。
- I left the project in capable hands.
- プロジェクトは信頼できる人に任せて離れた。
- =責任を“委ねて”自分はその場を離れる行為。
- プロジェクトは信頼できる人に任せて離れた。
▶︎「abandon」は放棄、「leave」は委任——責任の所在と感情の違いが明確。
② leave vs quit:制度的な離脱と継続性の違い
- She quit her job last week.
- 彼女は先週仕事を辞めた。
- =制度的な所属からの断絶。
- 彼女は先週仕事を辞めた。
- She left the company to pursue her own business.
- 彼女は起業のために会社を離れた。
- =目的を伴って所属を“離れる”移行的な行為。
- 彼女は起業のために会社を離れた。
▶︎「quit」は断絶、「leave」は移行——制度的な背景と意志の方向性が異なる。
③ leave vs let:能動的な手放しと受動的な許容
- He let the kids play outside.
- 彼は子どもたちが外で遊ぶのを許した。
- =許容・容認のニュアンス。
- 彼は子どもたちが外で遊ぶのを許した。
- He left the kids outside while he made a call.
- 電話中、子どもたちを外に残しておいた。
- =子どもたちをその場に“残して”、自分は離れた。
- 電話中、子どもたちを外に残しておいた。
▶︎「let」は許可、「leave」は残す——行為の主導性と意図が異なる。
④ leave vs remain:主語の視点と残存の焦点
- She remained in the room after everyone left.
- 皆が去った後も彼女は部屋に残っていた。
- =主語が「残る」ことに焦点。
- Everyone else left the room, but she remained.
- 他の人は部屋を去ったが、彼女はとどまった。
- =「leave」は去る側、「remain」は残る側。
- 他の人は部屋を去ったが、彼女はとどまった。
▶︎視点の違いが意味を分ける——「leave」は離脱、「remain」は滞在。
⑤ leave vs stay:動作の有無と意志の違い
- I stayed at home all day.
- 一日中家にいた。
- =静止・継続の意志。
- 一日中家にいた。
- I left home early in the morning.
- 朝早く家を出た。
- =自分の存在をその場から“移動させる”行為。
- 朝早く家を出た。
▶︎「stay」はとどまる、「leave」は動く——行動の有無と意志の方向性が対照的。
このように、同じ「去る」「残す」「任せる」と訳される単語でも、英語では「放棄」「制度的離脱」「許容」「残存」「静止」など、細かなニュアンスの違いが存在する。
「leave」はその中でも、「何かを残して自分は去る」ことで空間・責任・制度・心理に変化を生じさせる、抽象的かつ柔軟な動詞である。
次章では、こうした違いを踏まえたうえで、実践的な使い方を確認していく。
5.実践:文脈で使い分ける
以下の文の空欄に、適切な語句(leave / abandon / quit / let / remain / stay)を入れてみよう。
文脈に応じたニュアンスの違いを意識することで、単語の選択精度が高まる。
- I decided to ___ the company to start my own business.
- (自分のビジネスを始めるために会社を辞めることにした)
- 答え:leave ※制度的な所属を“離れて”、新たな目的へと移行する行為。
- She ___ her job without notice.
- (彼女は予告なしに仕事を辞めた)
- 答え:quit ※制度的な断絶。継続性を断ち切る意志。(leftも可だが、より中立的な語であり、突然さや断絶のニュアンスは弱め)
- He ___ the dog tied to a tree and walked away.
- (彼は犬を木に繋いだまま放置して立ち去った)
- 答え:abandoned ※責任を放棄した否定的なニュアンス。
- Please ___ me finish this on my own.
- (これを自分で終わらせるのを許してほしい)
- 答え:let ※許容・容認のニュアンス。能動的な手放しではない。
- She ___ in the room long after the meeting ended.
- (会議が終わった後も彼女は部屋に残っていた)
- 答え:remained ※主語が“残る”ことに焦点。静的な状態。
- I decided to ___ at home instead of going out.
- (外出せずに家にいることにした)
- 答え:stay ※動作を起こさず“とどまる”意志。
- He ___ the door open while he went to get the mail.
- (彼は郵便を取りに行く間、ドアを開けたままにしておいた)
- 答え:left ※状態を“そのまま残して”、自分はその場を離れる。
このように、同じ「去る」「残す」「任せる」「辞める」と訳される行為であっても、文脈によって選ぶべき単語は異なる。
- leave:空間・責任・制度・心理の境界を“残して去る”抽象的な動詞
- abandon:責任放棄を伴う“見捨てる”行為
- quit:制度的な所属からの“断絶”
- let:受動的な“許容”
- remain:主語が“残る”ことに焦点
- stay:その場に“とどまる”意志を示す
それぞれのコアイメージを把握することで、場面に応じた語の選択がより的確に行えるようになる。
ここまでの整理を踏まえ、最後に「leave」の意味を簡潔にまとめておこう。
6.まとめ:「leave」は“残して去る”感覚でとらえる
「leave」は、空間・物・責任・制度・心理など、さまざまな対象を“残して去る”ことで変化を生み出す基本動詞である。
その多義性は、「何かをその場に残し、自分はそこから離れる」という構造に根ざしており、文脈に応じて「去る」「残す」「任せる」「辞める」「放っておく」などの意味を担う。
このイメージを軸にすれば、訳語の違いに惑わされず、場面ごとの使い分けも自然にできるようになる。
語義の暗記ではなく、「何を残し、どこから離れるのか」をイメージすることが、「leave」を語感を伴って使いこなすための近道となる。

